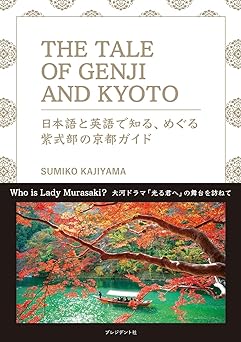「ひねり仕立て」という匠の技も
また、忘れてはいけないのが、平安装束には、日本が1000年以上にわたって受け継いできた技術が詰まっていること。その一例が、狩衣の縁などの「ひねり仕立て」。(袷ではなく)ひとえ仕立ての装束に用いられる伝統技法です。
糸を使わず、布の端に薄く糊をつけ、こよりを巻くように、くるくると丸めるのですが、ひねり方がゆるいと、ふわっとした仕上がりになってしまいます。針金が入ったように細くハリのある縁になるようひねり込むのが熟練の技。角の処理は特に難しいそうですが、夫である、装束司の福呂淳(きよし)さんは「名人級の技を持っている」と、福呂一榮さんは胸を張ります。
「糊は、ゆがいたお餅を板の上に広げ、すりこぎで力を込めて練ってつくります。糊の練り方が悪かったり、布のひねり方が弱いと、縁がほつれてしまうんですよ。なので最近では、糊にボンドを混ぜて制作される方もおられるようですが、主人は昔ながらの手法を守っています」
糊から手づくりとは、途方もなく手間暇のかかる仕事です。それゆえ、こうした技法で仕立てられた装束は、現在では希少なものになっているとか。平安装束は、日本の美と匠の技が凝縮された文化遺産といえるかもしれません。