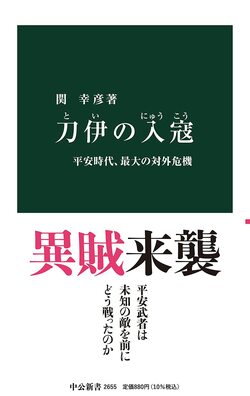刀伊による横暴
この突発的な「賊徒」の来襲は即日、対馬から通報がなされ、4月7日に大宰府に伝えられた。また壱岐島分寺講師(国分寺に置かれた僧侶)の常覚も、単身脱出して同じ日に大宰府に着き、壱岐守藤原理忠以下、多くの島民が殺されたことを報じた。
刀伊の兵船は、大宰府に一報が伝えられた4月7日には既に筑前(福岡県北西部)の沿岸に現れ、怡土(いと)・志摩・早良(さわら)の3郡に侵攻。「人・物ヲ奪ヒ民宅ヲ焼ク」などの横暴をなした。
賊徒の船の長さは12尋(ひろ)から8~9尋で、船には楫が三、四十ばかり取り付けられ、五、六十人から二、三十人の人々が乗船していた。
彼らは刃を振り回し、弓矢を持ち、楯を保持していた。
戦闘部隊が繰り出され、山野を駆け、乱暴を働いた賊徒は、牛馬を殺し食すなどの横暴に及んだ。
また老人や児童は斬殺され、「男女ノ怯者(抵抗しない者)」は船に載せられ、数は四、五百人に及んだ。さらに各地で穀米が奪取され、被害は甚大だったという。