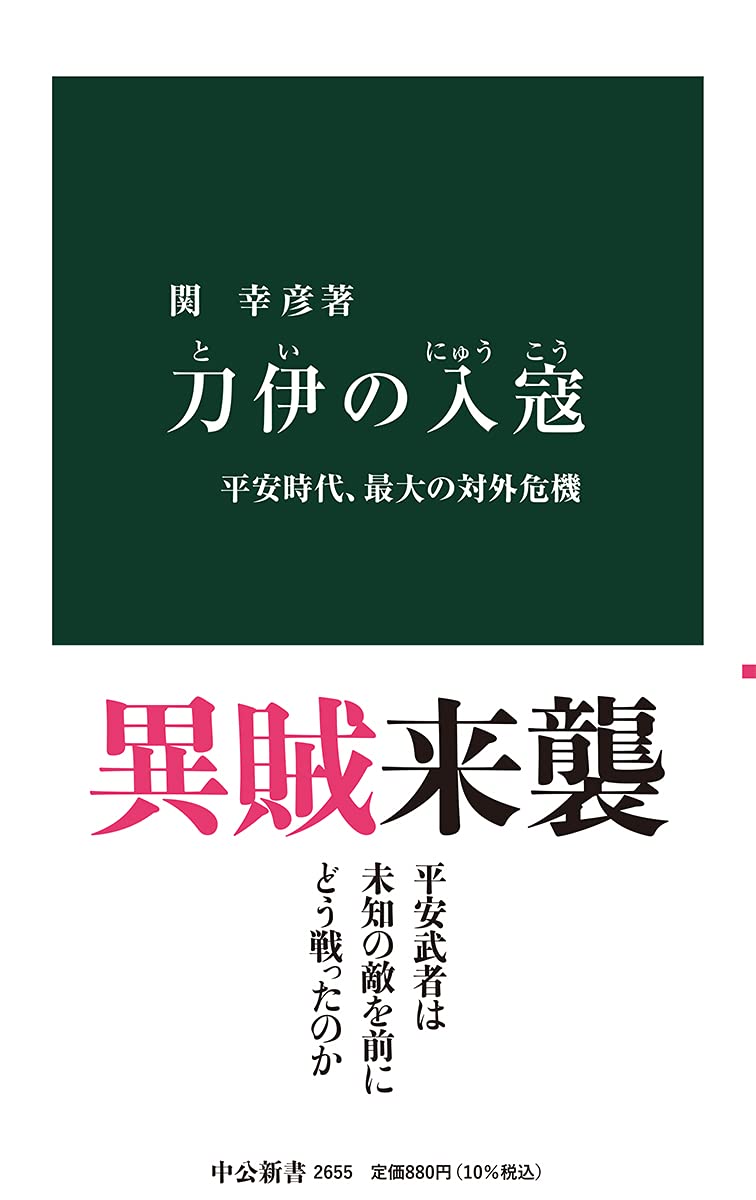事件の経過
戦闘後に捕虜を尋問したところ、いずれも高麗の人だったという。彼らは対馬来襲以前に賊徒軍に捕らえられた人々であった。
以上、『朝野群載』所収の4月16日付の「大宰府解状(げじょう)」からの要約である。長文で内容は多岐にわたるが、刀伊来襲のおおよそが理解できるだろう。
この解状にもとづき、改めて日付ごとに事件の経過を整理すれば、左のようになろうか。
・3月28日 刀伊軍、五十余艘で対島・壱岐に来襲。
・4月7日 対馬・壱岐両島を攻略後、筑前国怡土・志摩・早良3郡に侵攻。
・4月8日 那珂郡能古島を攻略、同島に刀伊軍布陣。
・4月9日 刀伊軍、博多警固所を襲撃。
・4月12日 刀伊軍、志摩郡沿岸を攻略。
・4月13日 刀伊軍、肥前国松浦郡を侵し退去。
*本稿は、『刀伊の入寇-平安時代、最大の対外危機』の一部を再編集したものです。
『刀伊の入寇-平安時代、最大の対外危機』(著:関幸彦/中公新書)
藤原道長が栄華の絶頂にあった1019年、対馬・壱岐と北九州沿岸が突如、外敵に襲われた。東アジアの秩序が揺らぐ状況下、中国東北部の女真族(刀伊)が海賊化し、朝鮮半島を経て日本に侵攻したのだ。道長の甥で大宰府在任の藤原隆家は、有力武者を統率して奮闘。刀伊を撃退するも死傷者・拉致被害者は多数に上った。当時の軍制をふまえて、平安時代最大の対外危機を検証し、武士台頭以前の戦闘の実態を明らかにする。