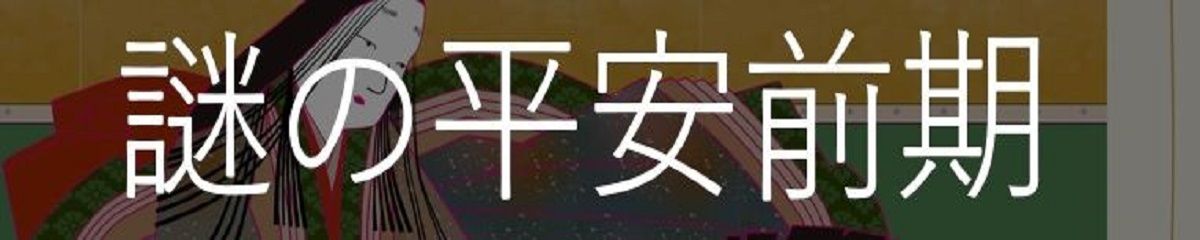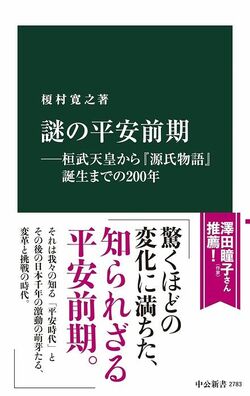平安時代には「適齢期」「ちょうどいい年の差」という意識はなかった
よく「20代半ばで独身だった彼女に焦りがあり、父親同様の年齢の男でも選んだ」と言われますが、平安時代には「適齢期」や「ちょうどいい年の差」という意識はなかったと考えられます。
『源氏物語』の光源氏の恋人や妻は、年上の六条御息所、大学生と小学生が出会った感じの紫の上、ライバルの娘の玉鬘、兄の娘の女三宮など娘でも不思議でない世代まで、実に幅広いのです。
また、若い頃の光源氏に言いよる老女官の源典侍のような女性も出てきます。
実在の女性でも、冷泉天皇の皇子二人と恋をして「恋多き歌人」として有名な和泉式部は30代後半でも恋愛をしています。
そもそもこの時代の結婚は、男が何人もの女の元に通う「通い婚」から始まり、相性や社会的・経済的事情から最終的に同居する「正妻」とそれ以外の「妾」という形にまとまるので、年の差などはケースバイケースなのです。