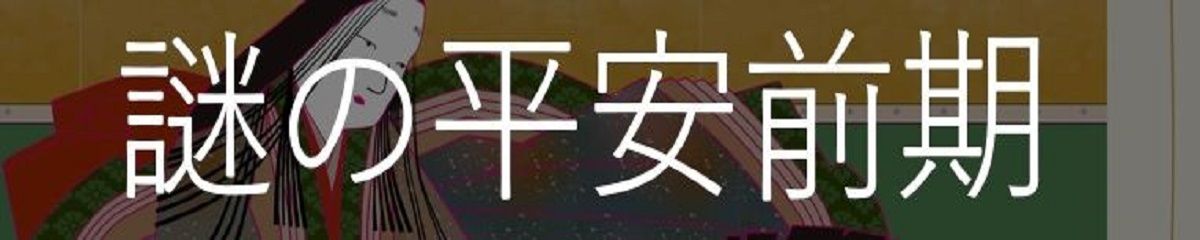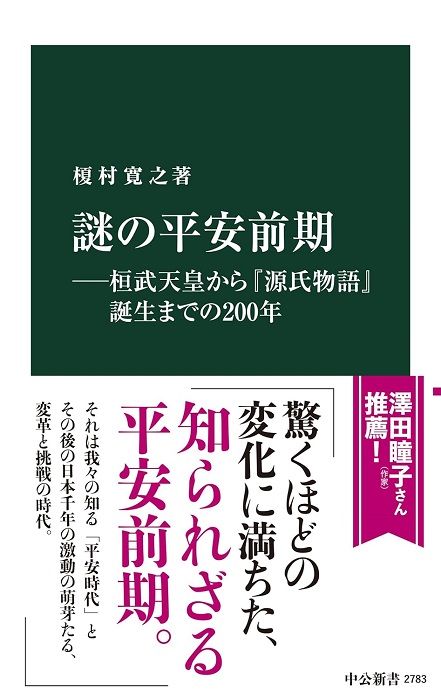宣孝の狙いは娘婿が叶えたのかも
とすれば、同じ一族で、高藤の甥の中納言藤原兼輔、この血統のもう一人のエリートの子孫である紫式部との結婚にも、やはり思惑があったと想像できます。
父の為時の越前守抜擢が、宋の商人との対応を目的としていたという最近の説を踏まえれば、外来貿易を視野に入れた学者官僚との結びつきにも魅力を感じたのかもしれません。
このように宣孝の思惑を考えると、為時の家産を受け継いだ紫式部は利基流藤原氏のいわば代表として高藤流の宣孝を選んだのであり、軽々には離婚されない読みがあったようにも思えてきます。
実際宣孝の越前守の在任中に式部は帰京しているので、宋人と対応したことで話題の人、為時の邸の女主人として宣孝の訪れを待っていたのです。
二人の結婚は宣孝の予想外の早世により短期間で終わり、彼の本当の狙いはわからないままです。しかし彼の息子と娘は、親を越えて立身します。
隆佐と、後冷泉天皇の乳母となり、従三位の位を得て、「大弐三位」と呼ばれた紫式部の娘、賢子です。彼女の夫は高階成章といい「正三位大宰大弐(太宰府の次官で、現地支配者)」になります。大宰大弐は外来貿易でよく稼げる職務で、成章も「欲大弐」と言われました。
宣孝の狙いは娘婿が叶えたのかもしれません。
『謎の平安前期―桓武天皇から『源氏物語』誕生までの200年』(著:榎村寛之/中公新書)
平安遷都(794年)に始まる200年は激変の時代だった。律令国家は大きな政府から小さな政府へと変わり、豊かになった。その富はどこへ行ったのか? 奈良時代宮廷を支えた女官たちはどこへ行ったのか? 新しく生まれた摂関家とはなにか? 桓武天皇・在原業平・菅原道真・藤原基経らの超個性的メンバー、斎宮女御・中宮定子・紫式部ら綺羅星の女性たちが織り成すドラマとは? 「この国のかたち」を決めた平安前期のすべてが明かされる。