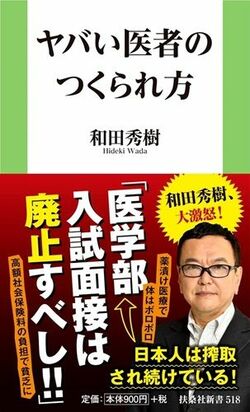判断の基準となるもの
ところがそれだと前任者の意向が働きすぎるということで、あるときから、前任の教授は教授選に参加してはいけないということになりました。
それ自体はもっともな話なのですが、そうすると、もともと教授の数が少ない眼科だとか、皮膚科などの次の教授は、その科の教授が一人もいない中で選ばれることになります。
大学病院というのは完全なる縦割り社会なので、よほど目立つことをしない限り、よその科の誰かの臨床の腕など知る由もありません。だから、判断の基準となるのは論文の数くらいしかないのです。
その結果、論文をせっせと書くような人しか教授になれなくなり、いつの間にか「研究重視・臨床軽視」にどんどん拍車がかかってしまったのです。