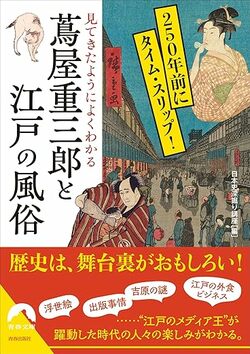庶民の生活を描いた風俗画を「浮世絵」と呼ぶようになった
「浮世絵」の始祖は、江戸初期に活躍した菱川師宣(ひしかわもろのぶ)です。
肉筆画では、後述する『見返り美人図』などを描き、また「浮世絵版画」も手がけ、1670年代、「墨刷り絵」と呼ばれる白黒の版画をつくりました。当初の浮世絵は、カラフルなものではなく、墨1色刷りのモノクロ版画だったのです。
浮世絵の世界では、連作版画を「揃物(そろいもの)」と呼びますが、その出版スタイルを生み出したのも、彼でした。
師宣は、それまでは、本の一部(挿絵)でしかなかった版画を本から切り離し、独立のアートに変えたのです。「浮世絵の始祖」といってもいい存在でしょう。
ただ、そこから、私たちがよく知る多色摺り、フルカラーの浮世絵になって、人気を得るようになるまでは、約1世紀の時間を要しました。
そのきっかけは、浮世絵とは別のところにありました。明和年間(1764〜1772)、江戸の裕福な趣味人の間で「絵暦(えごよみ)」の交換会が流行したことが発端になったのです。
絵暦は、今でいえば、イラスト付きのカレンダーのようなもの。当時の暦(太陽太陰暦)では、毎年、何月が「大の月」で、何月が「小の月」なのか、一定していませんでした。