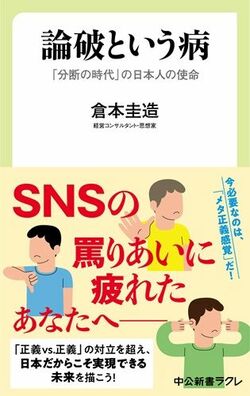水と油
こういう提言は過去20~30年の日本で掃いて捨てるほど繰り返されてきたのに、なぜ日本は変われないのか? それは結局「自分は世界の半分しか代表していない」という謙虚さが欠如しているからだといえるでしょう。
本の前半で語られているような、外資系企業で成功した自分のやり方を日本国民全員に押しつけると、後半に出てくる「日本の強み」が崩壊してしまうかもしれない、という「一周回った因果関係」に無自覚すぎると、結局、平成の議論vs.昭和の議論の永久戦争になってしまうのです。
「世界の逆側には自分とは全く別個の論理で動き、彼らなりの強みの源泉を生み出している存在がいる」という発想に立つことによってのみ、自分たちの強みと相手側の強みを両立する、「多様性を超えた連帯」が可能になる。
水と油はコトワザになっているぐらい「混ざらない」存在ですが、乳化剤という成分を追加すると「混ざり」ます。
水と油が混ざった状態の物質を「エマルション(乳濁液)」と呼びます。身近な日常生活の中では、マヨネーズやバターなどが挙げられます。そして食器洗い洗剤が食器にこびりついた油を水に取り込んで流せるようにするのも同じ仕組みです。
水は水の性質を保ったまま、油は油の性質を保ったまま、いかに混ぜ合わせ、協業するか?
「マヨネーズを作る」発想を持てるかどうかが、これからの日本の復権には必須なのです。