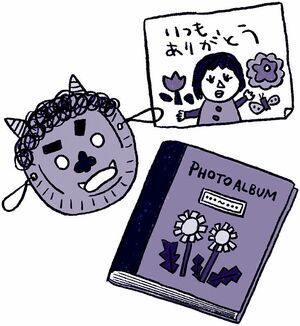では、手放せない理由は何なのか。これもいくつか要因があります。
まず、手に入れる時と同様に、「リスク回避」が挙げられるでしょう。これを捨ててしまったらあとで困るかもしれない。いざという時のためにとっておいたほうがいい、という心理です。
そのほか、「まだ使えるのにもったいない」と考えるケース。新しいタオルがたくさんあるのに、使い古されたタオルばかり使っているお宅をよく見かけます。「もったいない」がいきすぎたり、長年使っているほうが使い勝手がよかったりするのが理由のようです。使っていない食器や洋服も同じような理由が考えられるでしょう。
そして、思い出にひもづいたモノへの愛着も手放せない理由のひとつ。さらに、「ミスをしたくない」という心理も理由になります。たとえば、書類などを「処分して困ったらどうしよう」というものです。
これらの心理は、高齢者になるほど、より強くなる傾向があります。家族を失ったり、自身の健康を損ねたり、社会とつながりが希薄になったりという経験を重ねると喪失感を覚えるようになり、モノを失うことにも抵抗が出てくるのです。
そうなるとモノを手放すのがどんどん困難に。けれど、体力・気力・行動力などが衰える高齢者ほど、安全感のためにも、スッキリ片づいていたほうが望ましいのです。