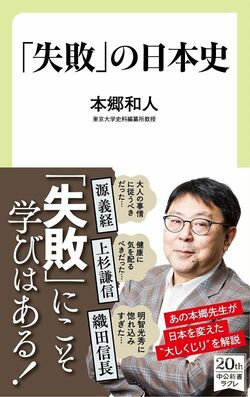家康が“徳川”と名乗るまで
天正14年(1586年)9月7日、徳川家康は遠江の鴨江寺と大通院に対し判物を出しています。尾の署名は2通共に「三位中将藤原家康」です(御庫本古文書纂)。
源氏でないことは一目瞭然ですね。
先学の研究によると、この頃は藤原と源の両方を使っていて、天正20年(1592年)より以降は確実に源を名乗っているそうです。
ということは、家康が新田氏の一族である得川氏の子孫というのは、かなり怪しいということになります。
得川というのは、新田義重の4男である義季が、上野国の新田荘内の得川郷(現在の群馬県太田市徳川町)の領主となり、得川四郎と称したことに始まります。
家康はこの子孫を称し、「得」を嘉字(良い意味を持つ字)である「徳」に変えて、名乗りとしたのです。