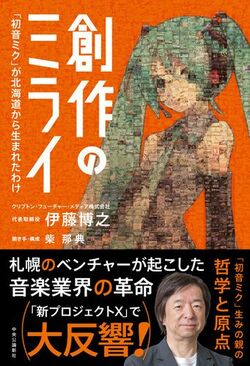声優さんに歌ってもらったら面白そうだな
初音ミクの企画が始まったのは2006年の秋ごろ。当時の社員数はまだ10人から20人くらいでした。ヤマハさんから「新しいVOCALOIDエンジンを開発中なので、ぜひ製品化を考えてください」という連絡がありました。初代よりも人間に近い、自然でなめらかな歌声を再現できる技術になっていて、その頃からいろいろと考え始めました。初音ミクの開発を担当した佐々木渉は、その頃は入社1年目でしたね。
「MEIKO」と「KAITO」の経験から、パッケージにアニメ風のイラストを取り入れること、女性の歌声にすることはすぐに決まりました。でも、声の収録をオファーする段階で、連絡した女性ミュージシャンに軒並み断られてしまった。自分の声のクローンがつくられてしまう、といったような心配が彼女たちの中にあったようです。
「MEIKO」と「KAITO」ではプロのシンガーとして活躍されている拝郷メイコさんと風雅なおとさんにお願いして、歌声を提供していただきました。歌がうまい方に歌声を提供してもらって、実在するシンガーの歌声で歌うソフトウェアをつくろう、という考え方だった。でも、ボーカロイドがより人間に近い歌声を再現できるようになったことで、発想の転換が必要になった。
そこで僕の中に浮かんだのが、声優さんに歌ってもらったら面白そうだなというアイディアでした。
ボーカロイドの歌声合成技術は「素片連結型」というもので、人の歌声から切り出した素片を連結して、なめらかに声らしくして合成するものです。原理的にはサンプラーに近いものがあります。
だから、声優さんが演じている「可愛い」や「かっこいい」といったキャラクター性のある声の波形を取り入れて合成できれば画期的な製品がつくれそうだと思った。それによって誰かの再現ではない、新しいキャラクターのようなものを創り出せれば、それを使って新しい音楽を創ろうと思う方が出てきてくれるかもしれない。それが新しい音楽を創るための土台となり、何か面白い文化が生まれるのではないか。そういう期待がありました。