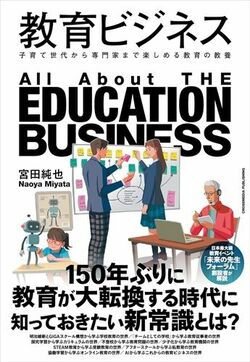公教育と産業が円滑に接続されていた時代
明治から昭和の時代は「機械」が主役の時代でした。機械を人間がどのように活用し、大量生産を実現するかが焦点になっていました。
達成すべき目標が明確な工業社会では、マニュアル化された仕事が中心です。近代学校教育制度は、このような工業社会のニーズに応え、人材の「標準化」を国家単位で成し遂げて効率的な工業化を果たすために貢献していました。受験は、どれだけ知識を詰め込み、その中から適切な答えをどれほど素早く出せたかを「正答率」という物差しで計測するものとして、工業社会に適応する人間を選抜する社会的な機能を担うものでした。
よい学校に入れたということは、その優位性を客観的に示す証であり、それがよりよい就職につながる社会でした。よい学校に入れば、よい会社に入って悠々自適で豊かな老後を送るための資格が得られる。社会が創り出した目標や価値観を実現するため、一元的な価値観にもとづいたピラミッド型階層のなかで、より上位の組織・より上位の立場へと上がっていくことが望ましいとされるようになったのです。
この時代には、公教育で「知識」を習得することが仕事で活躍することに直接つながっていました。つまり、公教育と産業は円滑に接続されていたのです。この円滑な接続が日本の発展の両輪となり、今日の日本があります。受験は大きな社会的役割を果たしていたのだと言えるでしょう。
しかし、公教育で得た知識と仕事が円滑につながる時代は終わりを告げたのです。