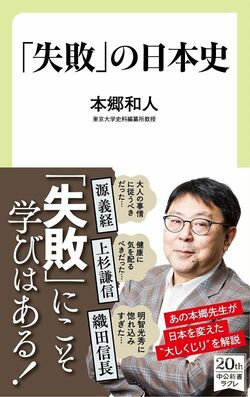天明の大飢饉とは
「べらぼう」中で描かれている天明の大飢饉は、江戸時代中期の1782年(天明2年)から1788年(天明8年)にかけて発生した飢饉です。
江戸四大飢饉(寛永、享保、天明、天保)の1つで、日本の近世では最大、最悪の飢饉とされます。
東北地方は1770年代から、主に冷害によって農作物の収穫が激減しており、農村部はすでに疲弊している状態でした。天明2年(1782年)から3年にかけての冬は暖冬で、約30年前の宝暦年間に凶作が続いたときの天気と酷似している、との指摘は当時から存在したようです。
人々が不安に思う中、天明3年3月12日には津軽の岩木山が、7月6日には信州の浅間山が噴火し、各地に火山灰が降りました。
火山の噴出物は成層圏に達して陽光を遮り、日射量が低下して冷害がさらに悪化。このため農作物に壊滅的な被害が生じ、翌年から深刻な飢饉状態となりました。