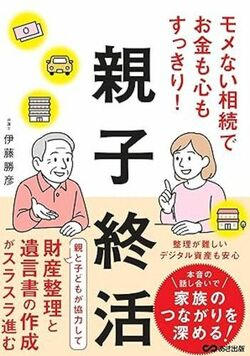遺留分を意識した財産分け
遺言の記載内容は自由度は高いものの、完全に自由というわけではありません。民法では、一定の法定相続人に「遺留分」という権利が認められています。
遺留分とは、相続財産の一部について、遺言などで侵害できない最低限度の取り分のことです。
遺留分が認められるのは、配偶者、子(および孫など直系卑属)、直系尊属(親・祖父母など)です。きょうだいには遺留分はありません。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の1/3、それ以外は1/2です。この割合を各相続人の法定相続分に乗じたものが、各相続人の遺留分となります。

遺留分は配偶者、子は1/2で、直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の1/3となる。<『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』より>
例えば、配偶者と子2人が相続人の場合、法定相続分は配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4です。遺留分はその1/2ですから、配偶者の遺留分は相続財産全体の1/4、子の遺留分はそれぞれ1/8ずつとなります。
遺言書の作成では、この遺留分を侵害しないように配慮することが重要です。もし遺留分を侵害するような内容の遺言を作成すると、侵害された相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。
この請求が認められると、その部分については遺留分が金銭で交付することで調整され、遺言者の意思通りの相続ができなくなることがあります。
ただし、遺留分はあくまで権利であって請求が義務付けられているわけではありません。相続人が請求しなければ問題は生じないのです。家族間の理解と納得があれば、遺留分を下回る相続でも円満に進むことは少なくありません。