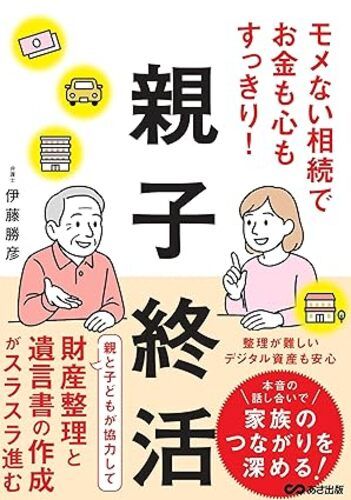寄与分とは
一方、寄与分とは、亡くなった人の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人がいる場合、その貢献度に応じて相続分に加算される部分です。
例えば、家業を手伝って売上増加に貢献した、無償で介護を長期間行った、医療費を負担したなどの場合が当てはまります。
寄与分の認定には、その貢献が「特別の寄与」であることが求められます。普通の親族としての協力義務を超える貢献であり、かつ無償または低い報酬での貢献であることが条件です。例えば、同居して家事を手伝う程度では通常は認められませんが、仕事を辞めて長期間の介護を行った場合などは認められる可能性があります。
寄与分の主張は、相続人間の遺産分割協議で行うのが一般的です。合意が得られない場合は、家庭裁判所での調停や審判で決定されます。なお、寄与分を主張できるのは相続人だけですが、相続人でない親族が被相続人の財産維持や増加に後見したことに対して、「特別寄与料」が請求できます。
特別受益と寄与分は、遺産分割の公平性を確保するために重要な考え方ですが、その評価は必ずしも簡単ではありません。特にお金での評価が難しい貢献(介護など)については、相続人間で意見が分かれることも少なくないです。
いずれにしても遺言書を作成するときには、特別受益と寄与分も考慮した上で財産分配を決めることが望ましいでしょう。例えば、「長男Aには生前に住宅資金として1,000万円を贈与したため、相続においてはその分を考慮する」「長女Bは10年間にわたり介護に尽力したため、**不動産を相続させる」のように明記しておくと、理解を得やすくなります。
※本稿は、『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』(あさ出版)の一部を再編集したものです。
『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』(著:伊藤勝彦/あさ出版)
本書では、家族全員で協⼒し合いながら親の終活をスマートに進めるための5つのステップを提供。
遺産相続や遺言書作成、金銭面における不安を大きく軽減するだけなく、親⼦のコミュニケーションが円滑になり、家族の絆も強化されます。