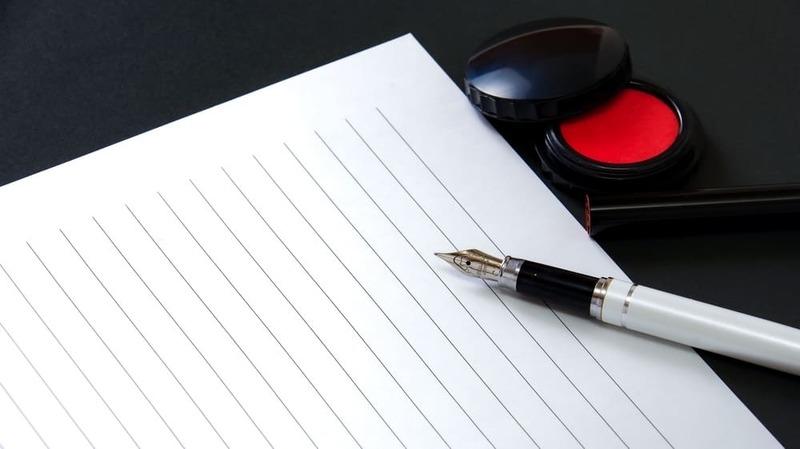親世代の高齢化や終活の内容の煩雑化が進んだ近年では、親世代が終活を一人で行うのは困難になってきています。そんななか、これまで終活に関する1000件以上の相談に対応してきた弁護士・伊藤勝彦さんは、家族一体となって親の終活に取り組む「親子終活」を勧めています。今回は、伊藤さんの著書『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。
遺言者自身の財産にのみ言及する
遺言書は自分の意思を死後に伝える重要な役割を担います。適切な遺言書を残すことで、相続トラブルを防ぎ、家族の負担を軽減することができます。
ここでは遺言書を最大限活用するために知っておくべき知識を解説していきます。
まず、遺言書に記載する財産は、遺言者自身の財産に限られます。配偶者との共有財産がある場合は、自分の持分についてのみ遺言できることに注意が必要です。生命保険の死亡保険金など、相続財産に含まれないものも遺言の対象外となります(生命保険の死亡保険金は、受取人の方の固有の財産となります)。
次に、遺言事項についてです。
遺言事項とは、遺言書に記載できる内容のことです。主な遺言事項は次の通りです。
遺言事項の種類
・財産の承継に関すること(誰にどの財産を相続させるか)
・相続分の指定(法定相続分と異なる割合で相続させる場合)
・遺贈
・遺言執行者の指定
・祭祀承継者の指定
・未成年の子の後見人の指定
・財産の承継に関すること(誰にどの財産を相続させるか)
・相続分の指定(法定相続分と異なる割合で相続させる場合)
・遺贈
・遺言執行者の指定
・祭祀承継者の指定
・未成年の子の後見人の指定
これらは具体的に記載することが重要です。
「自宅不動産を長男に相続させる」と書くとき、その不動産の所在地や登記簿上の表示を記載したり、「預金を分ける」場合では銀行名や口座番号を明記することが求められます。