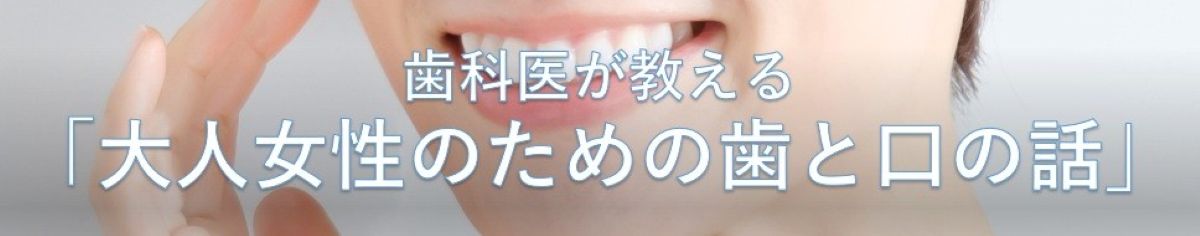(写真:stock.adobe.com)
「食事中にムセませんか?」「飲み込みにくくないですか?」 食事の様子を振り返って、答えが「はい」の人は、飲み込み機能(嚥下機能)が悪くなってきているのかもしれません。でも「いいえ」と答えた人の方が実は誤嚥をする可能性が高いかも、と聞いたら…きっと驚くのではないでしょうか? 誤嚥性肺炎が起こる意外なメカニズムと、今日から始められる予防対策について、幸町歯科口腔外科医院の宮本日出院長が分かりやすく解説します。
死亡原因第3位の肺炎。その原因の一つが…
口の中には、想像をはるかに超える大量の細菌が潜んでいます。
たとえば虫歯菌や歯周病菌以外にも大腸菌や肺炎菌など700種類もの菌がいて、耳かき1杯分の歯垢の中に1,000億個もの細菌があるとも。
そしてこれら口の中の菌が、お腹(消化器)でなく、誤って気管に入り込み、肺で炎症を起こすのが誤嚥性肺炎です。
三大疾病と言われる「悪性腫瘍」「心疾患」「脳血管疾患」は死亡原因のトップ3として有名ですが、2011年には肺炎が脳血管疾患を抜いて死亡原因の第3位になりました。
その肺炎にも種類があります。今や肺炎患者の約7割が75歳位以上の高齢者ですが、70歳以上が罹る肺炎のうち7割以上が誤嚥性肺炎で、高齢になるほどその割合が多くなります。
なぜ、高齢になるほど誤嚥性肺炎のリスクが高くなるのでしょうか?
これは老化と密接に関係していて、喉の筋力の低下が原因だからです。息をすると空気は肺に行きますが、飲んだり食べたりしたものはお腹に行きます。その行き先に誘導するのは喉にある弁のような蓋で、この蓋を操作するのが喉にある筋肉です。この筋肉が衰えてしっかりと役割を果たさなくなり、行き先を間違えて肺に誤嚥してしまうのです。