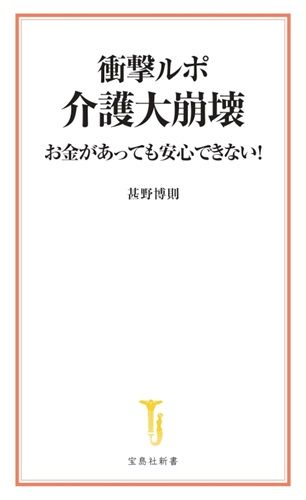検討会で議論された重要な課題
この検討会の内容を簡単に紹介しよう。まずはケアマネの業務について、その範囲の明確化が重要な課題として挙げられた。
ケアマネは利用者やその家族から多岐にわたる相談を受けており、介護サービスにとどまらず、日常生活全般に関する支援を求められることが多い。例えば、ゴミ出しや金融機関での手続きといった、本来の業務を超える依頼にも対応しているケースが多々見られる。こうした対応に関して、どの範囲までがケアマネの責任であるかを明確にすることが求められている。
また、緊急時の対応や家族への支援など、ケアマネに過度な負担がかかっている現状があり、それに対する評価や報酬の見直しが必要であるとの意見も検討会で出された。これらの過重な業務負担が、ケアマネの不足をさらに深刻化させている現状があるのだ。
主任ケアマネの役割についても、重要な課題が議論された。主任ケアマネは地域でのケアマネジメントの質を高める役割を担っており、他の職種との連携や、地域全体での支援体制の構築が求められている。しかし、現場では主任ケアマネが多くの時間を事務的な管理業務に割いており、その結果、現場での指導や他のケアマネの育成に十分に時間を割けていない。
このような状況を改善するためには、管理業務を効率化し、主任ケアマネが本来の役割に集中できる環境を整えることが必要である。主任ケアマネが本来の役割を果たせないことが、現場におけるケアマネ不足をさらに悪化させているのだ。
人材確保に関する議題も重要な焦点であった。ケアマネの資格を取得しても、実際に業務に従事する人が少ない現状が問題視されており、資格取得の条件を緩和すること、研修制度を見直すことが検討されている。
また、ケアマネの離職防止や、離職したケアマネの職場復帰を促進するための対策として、研修の柔軟化や待遇改善が求められている。ケアマネが業務の厳しさや低賃金を理由に離職するケースが多く、このままでは人材不足が深刻化することが懸念される。
※本稿は、『衝撃ルポ 介護大崩壊 お金があっても安心できない!』(宝島社)の一部を再編集したものです。
『衝撃ルポ 介護大崩壊 お金があっても安心できない!』(著:甚野博則/宝島社)
絶望的な人手不足、高齢化する介護職員、虐待を放置する悪徳施設、介護保険と介護ビジネスを食い物にする輩――。
「団塊の世代」が全員75歳以上になる2025年は「介護崩壊元年」とされるが、現場ではすでに崩壊は始まっている。
タブーな介護現場のリアルを、実例とともに徹底レポート。