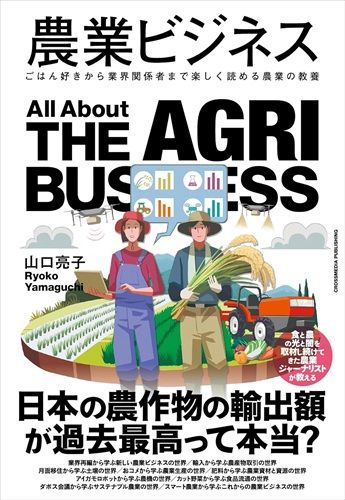有機農業の拡大への寄与
アイガモロボ開発のきっかけは、中村さん自身が有機米の栽培で苦労したことでした。
「雑草がどんどん生えてきて、除草作業の大変さを痛感しました。ロボットを使用して1人で栽培できる面積を広げることで、有機稲作の拡大につなげられないか。そう思ったのです」
こうして開発されたアイガモロボはすでに19代目となります。さらに、機能はそのままに「約16キロある重量を半分以下の約5キロに減らす」「田んぼの形状をアプリで設定しなくても自律航行できるようにする」「風への強度を高めて水田の均平がとれていなくてもある程度走行できるようにする」といった改良を加えた、より使いやすく、安価なモデルを開発しました。2025年3月に27万5000円で発売しています。
有機稲作に取り組む農家はもちろん、山梨県のJA梨北や石川県のJAはくいと提携するなど、アイガモロボ利用に積極的なJAも増えつつあります。
田植え後の水田を、アイガモロボが走り回る――。そんな光景が、地域の日常になるかもしれません。
※本稿は、『農業ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。
『農業ビジネス』(著:山口亮子/クロスメディア・パブリッシング)
斜陽産業と思われがちな農業に、大変革が起きている!?
9つの切り口から、綿密な現場取材とデータ分析に基づく農業現場の実情と最新事例を紹介。
日本人の「食」に直結し、テクノロジーによって進化を続ける「巨大市場・農業」の“いま”と“これから”を伝える1冊!