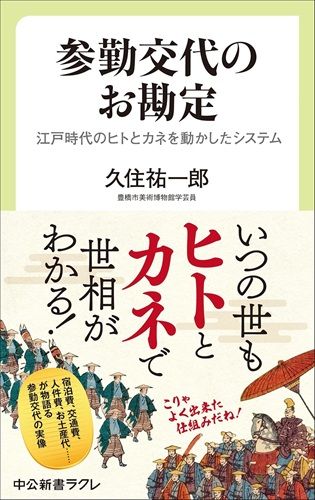参勤交代経費の比較
岡山藩では参勤交代ごとに金3000両(2億8800万円)ほどの予算を定めており、総額が予算内に収まった場合は残額を藩主の御手元金に入れ、逆に予算オーバーした場合は不足分を御手元金から補填していた。
河川の増水などで足止めされた年は総額が多くなるが、文化年間まではほとんどの年で予算内に収まっていたものの、文政年間には恒常的に予算オーバーするようになっていた。この文政8年は加古川で1日足止めされ、結果的に金297両(2851万円)の赤字になった。
参勤交代の道中経費として紹介されることが多いのが、文化9年(1812)の鳥取藩の事例である。藩主池田斉稷(なりとし)が江戸から鳥取へ帰国した際のもので、総額は金1957両(1億8787万円)である。
内訳は、人足費が金847両(8131万円、43.3%)、駄賃が金492両(4723万円、25.1%)、修繕費を含めた諸品購入費が金387両(3715万円、19.8%)、川越賃・船賃などの運賃が金134両(1286万円、6.8%)、休泊費が金97両(931万円、5%)であった。
岡山藩と鳥取藩を比べると、石高が31万5000石と32万5000石、旅行日数が21泊22日と19泊20日である。したがって両藩の参勤交代の規模はほぼ同じであったと推定されるが、実際の道中費用は岡山藩の方が鳥取藩の2倍近く、約1500両(1億4400万円)も多くかかっていた。
両藩の内訳を比較すると、岡山藩で挙げた項目の(1)道中御供等経費と(6)女中旅費は鳥取藩の内訳に含まれておらず、2項目の合計がほぼそのまま両藩の経費の差異になっている。これらは鳥取藩でも発生している経費であり当然どこかで負担していたはずだが、支出するサイフが異なっているのか、道中経費とは別と考えられていたようである。このように、何を参勤交代の経費に入れるかは藩によって考え方が異なっていたことがわかる。
※本稿は、『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
『参勤交代のお勘定-江戸時代のヒトとカネを動かしたシステム』(著:久住祐一郎/中央公論新社)
幕府が大名の力を削ぐための施策であったという理解は今は昔。
最新の研究や詳細な史料をもとに、参勤交代の多面的な姿を明らかにする。
『三河吉田藩・お国入り道中記』で、三河吉田藩という一つの藩をマニアックなまでに掘り下げた著者が、経済や文化に多大な影響をおよぼした参勤交代の、巨大で豊かな全体像に迫る。