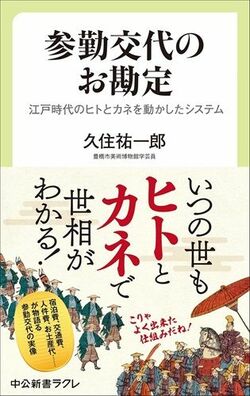三河吉田藩士の移動
安永6年(1777)4月時点の三河吉田藩士の居住地別の内訳を見ると、正規の藩士は飛び地も含めた国元が217人、江戸が210人とほぼ同数である。つまり、吉田藩士の約半分は定府であったことになる。足軽や中間も含めれば、江戸の吉田藩邸では687人が働いていた。定府の場合は彼らの妻子も一緒に藩邸内の長屋で生活していたため、藩邸内の居住者は1000人を優に超えていたことになる。
翌年の7月、吉田藩主松平信明は初めて吉田へのお国入りを果たした。この時御供として加わった67人の藩士のうち、吉田での詰切を命じられたのは藩主側近の20人ほどしかいなかった。残りの藩士は数日間の休暇の後、数人のグループごとに江戸へ立ち帰った。定府の藩士が半数を占める吉田藩では、あえて勤番をさせる必要がなかった。
松平信明がその後長きにわたって幕府の老中を務めたように、吉田藩主は幕府要職に就くことが多く、長期間参勤交代をおこなわないことも珍しくなかった。その間は、ただでさえ少ない勤番の藩士がさらに少なかったということである。
とはいえ、それでは国元の藩士が藩主に直接奉仕する機会がなくなってしまうため、1年や半年交代で勤番の藩士が派遣された。信明が老中を務めていた寛政年間には、足軽大将である者頭(ものがしら)の藩士1人が配下の足軽十数人を連れて勤番を務めたほか、藩主の身の回りの世話をする近習も2~3人ずつ交代で江戸へ出てくることが恒例になった。
つまり、寛政年間に吉田藩の江戸藩邸にいた勤番藩士は3~4人、足軽を入れても十数人程度であった。それ以外に、家老・中老・勘定奉行といった重臣たちが藩政について協議するために江戸へ出てくることがあった。