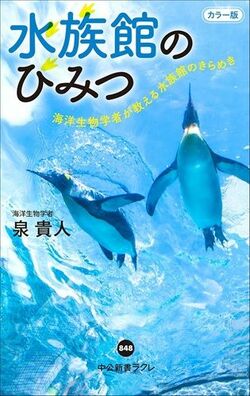迷路のような配管――覚えるだけでも一苦労
水族館の水槽の裏側にあるものを、もう少しだけ見ていこう。
まずは、複雑に張り巡らされた配管である。水族館は先述のように水を濾過・循環させて管理するのだが、当然それにも限界があり、ある程度は自然下から運んできた新鮮な水を加えてやらなければならない。
ここでは、多数派である海の生き物の水族館についてみてみよう*。
天然の海水は、近くの海から直接吸入して汲み上げるパターン(主に近くの海が比較的綺麗な場合)と、遠くの海からタンカーのようなもので運んでくる場合(近くの海が汚いか、もしくはそもそも水族館自体が海沿いにない場合)がある。後者の場合は、海水を貯蔵しておく巨大なタンクが必要だ。また、時には人工海水という、工業的に成分を似せてつくった海水の素を真水に溶かして使う水族館もある。
*ちなみに、淡水の水族館でも、ただ水道水を入れればいいというわけではない。日本の水道水は飲用に適するよう、塩素成分(いわゆる「カルキ」)などが配合されているからだ。中和するか、もしくは海水と同じように自然下から運搬してくるかである。
どちらにせよ、これらの新鮮な水が、持続的に水槽に注入されている。しかし、それだけでは水が増え、いずれ溢れてしまうから、逆に水を捨てる機構も必要だ。ゆえに、汚れた水の一部が、濾過の系列から外れて捨てられることになる。
まとめると、水槽の裏側には基本的に、水を注入する管、濾過槽につながる管、そして不要な水を捨てる管がある。さらには予備水槽にも同じ仕掛けがあったり、水槽同士で管がつながっていたり……となるので、最終的に一目ではどこにつながっているのかも分からない、迷路のような摩訶不思議な配管が形成されるのだ。
歴史の長い水族館ほど、この大量の配管はバリアフリーの対極のような配置になっていて、バックヤードで頭をぶつけるのは通過儀礼である。筆者の場合、たんこぶをつくるのは日常茶飯事、恥ずかしながらつなぎ目のボルト部分に頭をぶつけて流血したこともある(スタッフさんに心配をかけたくないので、必死で止血した)。