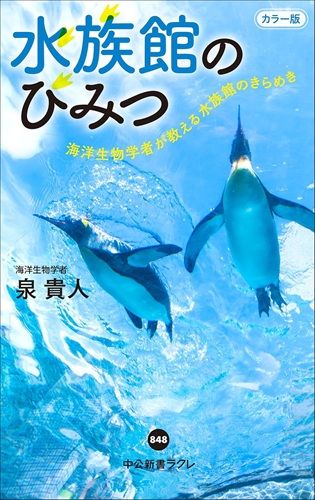“ゲーミング水槽”の裏側
また、特殊な例として、クラゲや金魚の水槽を、色のついたLEDで派手に照らしている水族館がある。赤、青、緑など、七色の光を刻々と変化させ、幻想的な空間を演出するのだ。
俗に我々マニアはこれを(派手な光を放つゲーミングパソコンになぞらえて)“ゲーミング水槽”と呼ぶ。あくまでこれはエンタメ的であり、生き物の健康に与える影響は正直「?」だが、話題性のためには仕方がないのであろう。この手のものが今後、増えていくだろうな。
なお、水族館は基本的にお客さんのいる館内が暗く、水槽の中がそれより明るくなるようにつくられている。足元が見えにくく不便に思うかもしれないが、これにはちゃんと理由があるのだ。
ガラスというものは、暗い側から明るい側はよく見え、その逆は見えにくい。ほら、昼間は窓の外がよく見えるけど、夜は窓に自分が映るでしょ? そのイメージだ。
これを水族館に置き換えると、観客側からは魚がよく見えるが、魚の側からは観客が見えにくくなっている。魚は比較的眼のいい生き物だから、ひっきりなしに人間が通ると、特に臆病な子はストレスを感じるらしい。それを室内を暗くすることで緩和し、なおかつ客の方は生き物がよく見えるってわけ。実に理にかなっているよね。
※本稿は、『水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
『水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』(著:泉貴人/中央公論新社)
水族館は、発見の宝庫だ。
日本全国の水族館の「表」も「裏」も、「酸い」も「甘い」も知り尽くした海洋生物学者が、水族館の真の魅力を解説する。
水族館が100倍楽しくなること請け合いだ。