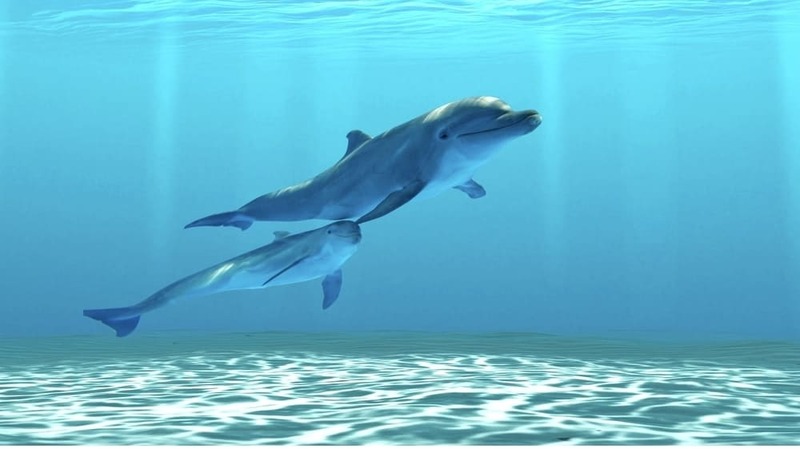これまで150以上の水族館を巡ってきた海洋生物学者・泉貴人先生は、「現代の水族館は、学者の目から見てもものすごい価値が眠っている、まさに“学術施設の極み”である」と語ります。そこで今回は、泉先生の著書『水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』から一部を抜粋し、水族館業界に通じるプロの目から見た、水族館のウラ話をご紹介します。
要らないものは持ってけや!――水族館の相棒は、漁師さん
漁師さんの仕事は、主に網を海に投げ込んで、食用になる生物を獲ることだ。しかし、自然界の生物は、すべてが食用になるわけではない。言い換えれば、食用種も“食えない”生物も、一緒くたに網にかかってしまうのだ。これを「混獲」と呼ぶ。
さて、前者は売り物にすればいいとして、問題は後者だ。深場から網に絡めて引き上げてくるにもかかわらず、売り物にならない奴らは海に捨てることになる。海に返されたとて、元いた場所には基本的に戻れないから、多くの生物は生き永らえることは難しく、そのまま海の藻屑と化す運命なのだろう。
しかし! これを捨てないで済む方法がある。
もうお分かりであろう。そう、水族館だ!
水族館では、漁業的には有用でない生物も当然展示されている。特に深海の生物なんて、学者も見たことがないような珍しいものまで多種多様だ。それはつまり、混獲された生物が漁師さんから水族館へとわたり、水槽で貴重な展示生物となっているってこと。漁師にとっても、混獲された生物が(二束三文ではあるが)売れるし、何よりいらない混獲物を捨てに行く手間も省けるから、有難い話なのだそうだ。