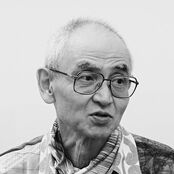短い災害をかわし長い恵みを楽しむ
鎌田 少し、気持ちに余裕を持ってポジティブに考えてみましょう。そもそも「100年に一度クラス」の巨大地震は、その後100年間は起きない、というわけです。巨大地震の前には複数のプレートが押し合うことで内陸の直下型地震が増えるのですが、この現象もひとたび巨大地震が起きるとしばらく静穏期に入ります。
実際に1946年の昭和南海地震の発生から内陸の地震は減り、次の活動期に入るまでの35年間、日本列島では大きな地震がありませんでした。
岸本 その間に、幸運にも日本は1960年代の高度成長期を迎えたのですね。
鎌田 巨大地震はもちろん恐ろしいけれど、乗り越えればまた平穏な数十年が始まる。十分な防災の備えと、一人ひとりが自分の身を守る意識を持つことで、再び豊かな社会を築くことができると私は思っています。
岸本 1年、2年の短い期間ではなく、先生は100年単位の長いスパンで世の中を見ていらっしゃるのですね。
鎌田 地球の歴史からいえば、46億年のうちのたった100年。それがまさしく、地学という学問の面白さなのです。
「短い災害と長い恵み」といって、たとえば京都は、東山・西山・北山のへりにある活断層が地震のたびに高くなって盆地ができ、そこへ鴨川が土砂を運んで平らで豊かな土地になった。そこに1200年続いた都が生まれたわけです。
富士山は噴火を繰り返して美しい姿になり、箱根山の地下ではマグマの活動で温泉が湧く。私たち日本人は揺れる大地にうまく適応しつつ、短い災害を経験や知識によって上手にかわし、長い恵みを楽しんで生きてきた。その点にも着目してもらえたら嬉しいですね。
岸本 複数のプレートがせめぎあう地震大国に生まれてしまったことを嘆くだけでなく、いかに日常を楽しみながら災害に備えるか。自分にも何かできるかもという希望が持てたことも、大きな収穫でした。今日はありがとうございました。
鎌田 こちらこそ、お話しできてとても楽しかったです。