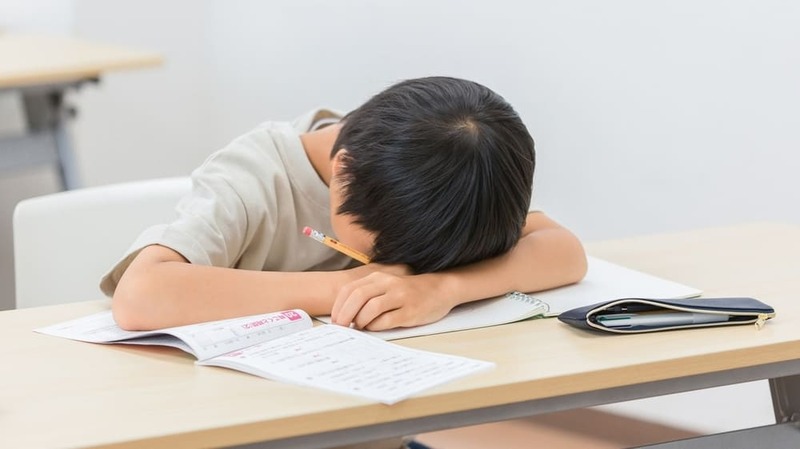文部科学省によると、2023年度に年30日以上登校せず「不登校」と判断された小中学生は34万6482人で過去最多となったそうです。不登校の児童生徒が増加するなか「じつは、子どもが抱える問題の背景には、親子関係をはじめとする家族の状況が深く関わっているケースが少なくありません」と語るのは、教育者・工藤勇一さんが信頼を寄せるスクールカウンセラー・普川くみ子さんです。そこで今回は、普川さんの著書『3万人の親子に寄り添ってきたスクールカウンセラーが伝えたい 10代の子どもの心の守りかた』から、親子コミュニケーションの極意を一部ご紹介します。
チャレンジを続ける・やめるは子ども自身に任せる
――立ち止まって考えることも立派な前進。人生はいつでも選び直せる
習いごとや受験など、子どもが取り組んでいるあらゆることにおいて、子どもが「やめたい」と感じているなら、私は「やめても問題ない」と思っています。
「石の上にも三年」「七転び八起き」と言われるように、日本語には継続の価値を重んじる言葉が多くあります。日本のように集団の調和を重んじる文化では、途中で物事をやめることは「周囲に迷惑をかける」「責任を放棄している」と受け取られやすく、自然とやめることへの抵抗感が強くなるのかもしれません。
同時に、日本は欧米に比べ「途中でやめる」「失敗する」ことに対する否定的な価値観が根強いように思います。とくに教育の現場では、「失敗から学ぶ」「方向転換も成長の証」といった考え方が、まだ十分に受け入れられていない印象があります。
私がこれまで相談を受けてきた親御さんからも、「やり遂げること」に価値を置くお話を多く伺ってきました。
「せっかく入った部活なんだから、三年間は続けさせたい」
「自分で『中学受験したい』と言ったから塾に入れたのに、まったく勉強しない」
などとおっしゃる様子を見ると、親としては「途中で投げ出すなんて根性がない」「自分に負けている」といった気持ちになるのでしょう。
ご自身がそうした価値観の中で育ち、努力の末に成功体験を得たからこそ、子どもにも「やり遂げる力」を身につけてほしいと願うのだと思います。
しかし、その「やり遂げる力」は、本当に子どもを幸せにするのでしょうか。