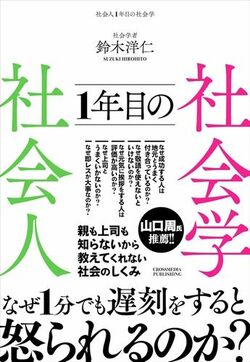社会には2つの「ルール」がある
英国の法哲学者ハーバート・ライオネル・アドルファス・ハートは、人に何かを求める「1次ルール」と、その範囲を決める「2次ルール」に分けました。では、この2つのルールのうち、就業規則は、どちらでしょうか? ひとまず、「1次ルール」だと言えましょう。
たとえば、就業規則によって、会社は、あなたに副業をしないよう求められます。この点で、たしかに当てはまります。ハートの表現を借りれば、「1次ルール」は義務を課すのです。
たとえば副業を考えましょう。副業の禁止や制限については、「企業秘密が漏洩する場合」や「競業により、企業の利益を害する場合」と、条件付きの場合が多いでしょう。副業しないように求めているものの、有無を言わさずではありません。「副業」が何を指すのかは、会社や職場によって違います。
就業規則は、単なるルールではありません。そこには、ルールの枠組みを決める、あなたと会社側、さらには、法律にかかわる人たちや、社会全体のさまざまな思惑が複雑にからんでいます。
このからみあいを、ハートは、ときほぐそうとしました。
法をめぐる哲学、といえば、社会学から遠く離れて見えるかもしれません。しかし、彼は、ルールを守るのは当たり前、とは考えません。そこに、社会学者に通じる考え方があります。彼の議論は、とても緻密で丁寧であり、いまもなお大きな影響力を保っています。
その議論が、頭でっかちではなく、現実に即しているのは、彼の経歴が影響しているでしょう。オックスフォード大学を卒業後、弁護士として働き、さらには、諜報機関MI5の一員を経て、法哲学者になりました。