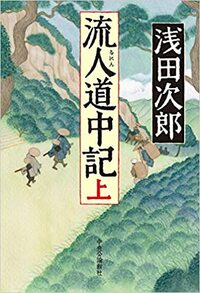がんじがらめにされている「家」をテーマに
杏 浅田さんの新作、『流人道中記』を拝読しました。不義密通の罪に問われるも切腹を拒否して蝦夷への流罪となった旗本・青山玄蕃と、その押送人である19歳の見習与力・石川乙次郎の二人旅。二人が行く奥州街道筋の風景や食事の描写も素敵で、その意味でもなかなか旅に出られない今、読むのにぴったりでした。あたかも、二人と一緒に東北を旅しているような気分になれましたから。
浅田 時代小説にも必ずテーマがあって、あの作品は率直に「武士とは何か」「家とは何か」なのです。罪を着せられた玄蕃が腹を切れば青山の家は安泰だったのに、そうしなかったために、家族も家来たちも路頭に迷うことになった。流人として一生恥を晒すというのは、当時の武士道にもとるものです。
杏 乙次郎には、それが許せなかったわけですね。
浅田 その考え方こそ、当時の武士のスタンダードだった。しかし、玄蕃は、その身をもって「命より大事な家とは、何なのだ」という根本的な問いかけをしたのです。
杏 江戸の世では、相当勇気のいる振る舞いだったはず。
浅田 武士はスーパーマンだったんですよ。司法も行政も立法も担って、軍事権も握っていたわけだから、その権力たるや現代の政治家なんて比べものになりません。それだけに、自覚とモラルがあって、そこから外れるのは並大抵なことじゃない。でも中には、物事を自由に見られた青山玄蕃のような人間もいたのではないか――いや、いてほしかった。
杏 そういう思いが、魅力溢れる人物を生み出すのですね。
浅田 武家社会のお話ではあるのだけれど、考えてみれば、今だって日本人は、家というものにがんじがらめにされているでしょう。普段は意識していないかもしれないけれど、ふとした瞬間に、生まれ育った家や嫁いだ家に帰属している自分に気づくわけです。
杏 たしかに「家とは何か」というのは、今も考える機会が多いです。旅の間に二人が遭遇した事件の中でも印象が強かったのが、騙されて強盗の手引きをしてしまい、主殺しで磔の刑を言い渡された丁稚の亀吉の一件です。牢につながれた16歳の少年が、なんとか助からないものか、と祈るような気持ちで読みました。ああいう場面を書くときは、作家さん自身の心も揺れたりするのですか?
浅田 あそこは、正直、「なんとかこいつを救う手立てはないものか」と自問自答しながら書きました。家族から命乞いまでされた(笑)。女房が「話があります」って言うから、なんだ、最近は悪いことなんかしてないぞと思ったら、「亀吉を助けてあげられませんか」と、真顔で言われて。
杏 痛いほどわかります。これ以上は控えますけど、先生がそこまで葛藤した末に導き出したストーリーだったことを知ると、あのシーンがより奥行きのあるものに感じられてきます。
浅田 そう言っていただけると、作家冥利に尽きますよ。