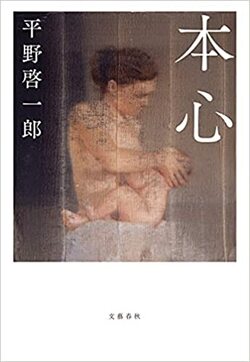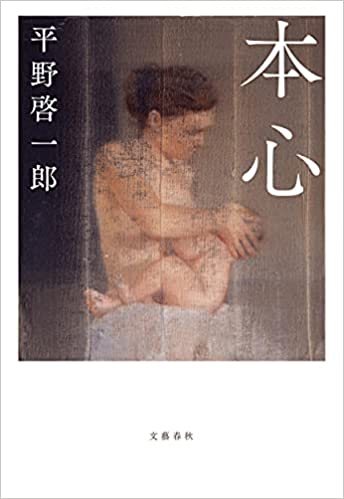人の“本心”はつくづくわからないもの
作中の世界は現在と地続きで、貧富の格差が固定化し、弱者が肯定感を持てない社会。未来と言わず、今を生きるのに精一杯な方は少なくありません。でも、自分を責めないでほしい。生活が苦しいのは、自己責任ではなく社会的要因が大きいのですから。自尊心を持てない方は、他者からの承認を求めるだけではなく、他者への小さな手助けを重ねてみてください。自分の価値を少しずつ信じられるようになります。
近年私は、たった一つの「本当の自分」など存在せず、対人関係ごとに見せる複数の顔すべてが「本当の自分」であるという「分人主義」を提唱しています。この小説でも、朔也の母が過去にどんな顔を見せていたかを浮かびあがらせました。朔也も依頼人に体を貸して命令通りに動く“リアル・アバター”の仕事をしながら、母の友人、車椅子のIT長者、ミャンマー人のコンビニ店員、母と縁ある作家と出会い、自分自身と向き合うことになります。
人の“本心”はつくづくわからないものです。最愛の母のことも100%理解することはできない。しかしそれでもわかろうと試みる。その揺らぎの中で、「他者であってもそこに愛はあるんだ」と次第にわかってくる。そんな“最愛の人の他者性”も、テーマの一つです。