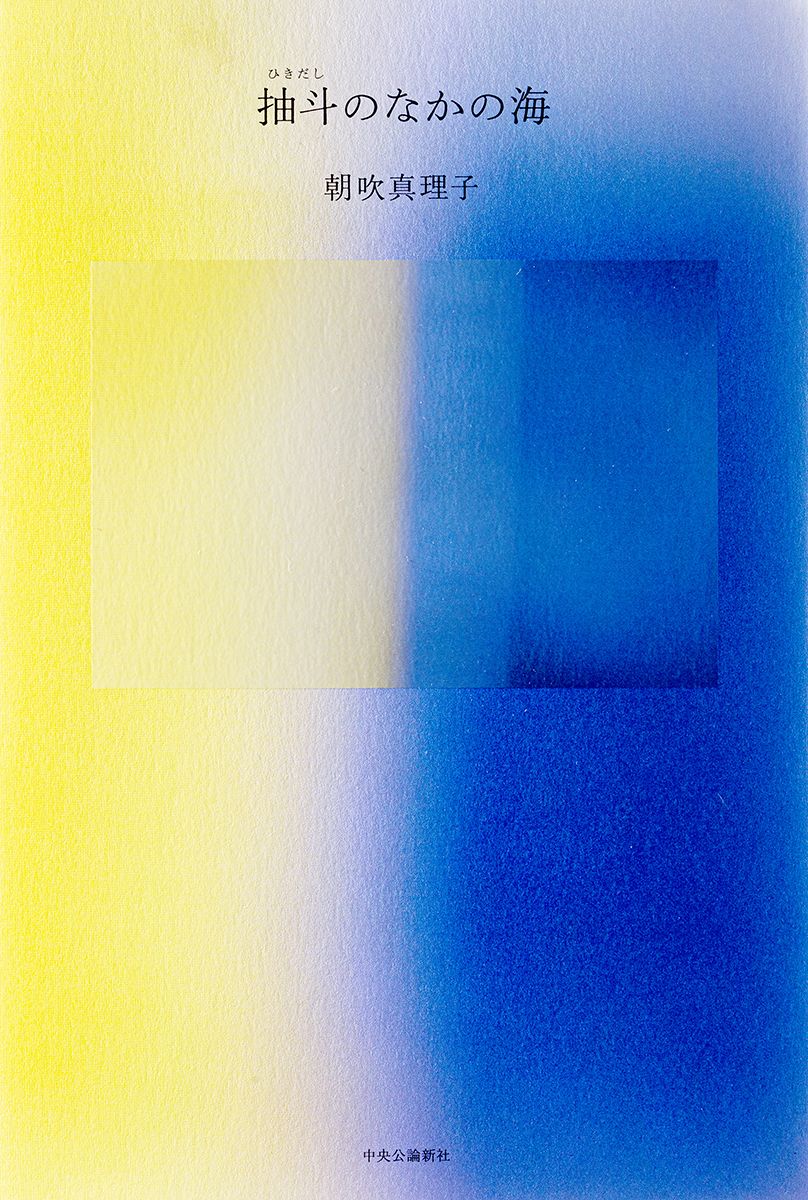かつての自分が書いた文章へ
デビューから今年で10年になりました。小説もエッセイも、書いた言葉を壜(びん)に詰めて、海に向かって投げるような気持ちで綴っています。誰とも知らない「あなた」に届くように祈って壜を投げて、それが偶然どこかに届く。そんな思いでひとつひとつ書いてきたエッセイのなかから、身辺雑記と本についての短文をまとめたのがこの本です。
装幀を手掛けてくださった近藤一弥(かずや)さんは、私のあこがれの方。デビューして間もない頃に偶然お目にかかった時の「いつかお仕事しましょう」という社交辞令を真に受け、今回お願いしました。各話の最後に昔の私に対して今の私からの返事を書いたのも、近藤さんとの打ち合わせで生まれたアイデアです。10年間のエッセイを読み返していると、いま考えていることと違ったりして、どこまで書き直すか迷っていた時、「かつて書かれた作品や音楽に、手紙を書くようなつもりで小説やエッセイを書いている」と近藤さんに話したら、「それなら自分が書いたものにも、自分の言葉で応答したら」と提案してくれました。
あらためて10年分を振り返ると忘れていたことも多く、知らない人の作品のようでした。エッセイの語源は「試み」。試みとしての文章って何だろう、自分の思考を練りながら綴るとはどういう行為だろう……。デビューしたての頃はそんな気負いと緊張がありましたし、プライベートを書くのが恥ずかしくもありました。でも、だんだん楽しんで書くようになったのが、読み返すとわかります。
鉱物への愛、将棋観戦記、家族への思い、武満徹やスーザン・ソンタグなど好きな本のこと。中学時代の昼休みにひとり講堂で澁澤龍彦を読んでいたエピソード、大好きな大江健三郎さんにお会いして失神した時のことも。臍(へそ)のごまを取ろうと竹串でつつき腹痛を起こした話も書きました。
そんなあほなことであれ、エッセイを書き終えるとちょっと寂しい気持ちにもなります。書いている出来事は、いつもすでに過去なんですよね。この瞬間は帰ってこない、無常迅速に時間が過ぎ去っていくと思うと、切ないです。
その一方で、矛盾しますが、いつまでも過去にならない時間もたくさんある。幼い頃、部屋の片隅で鉱物を口に含んでいた自分は、今もどこかにいるような気がする。他にもそういった時間が並行世界のように、いくつも存在するような感覚が自分のなかにあるんです。
未来の計画を立てることは、ほとんどありません。芥川賞をいただいた時、まだ大学院生で、社会経験がないまま気がつけば作家になっていました。寡作と言われますが、私にとっては小説が書きあがるのは奇跡。浮かんだイメージを文字として定着させたくて、ビジョンをつかまえて文章に落とし込む。書けば書くほどビジョンが移行していくので、また追って書く。その繰り返しで、書きあがらないのが当たり前。書けない悩みも、「次はこれを書きたい」という思いもありません。
無計画に生きていますが、これから年齢を重ねていくのはとても楽しみです。10代の頃は学校がとにかくつらかった。両親に「大人になると楽しいよ」と励まされていたのですが、今は本当にその通りだなと思っています。私の母は70代ですが、今がいちばん楽しいと言います。「残された時間が限られているから、悩んでいる場合じゃない」と、母は発表するあてのない小説や組曲を20年以上ひとりで作り続けているんです。私もこの先もっと楽しくなると信じています。