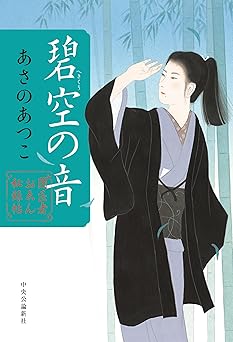三
吉原は遊女と客だけの世界ではない。
実にさまざまな見世が並び、さまざまな人々が生きて、働いている。
暮らしが根付いて、日々の営みが繰り返されている。
それなのに、現の生々しさはどこにもない。夜はむろん、日の光に照らされる昼間だとて、行き交う人々の姿も屋根瓦の照り返しも籬の弁柄色も、風のざわめきも三味線の音もことごとくが幻の衣を纏っているようだ。
蜃気楼(しんきろう)とは、蜃(みずち)が気を吐いたときに現れる楼閣のことだと聞いた。蛇に似ながら四脚を持つと言われる化け物が、吉原のどこかに潜んでいるのかもしれない。そんな埒もないことをつい考えてしまう。人の思案を誑(たぶら)かす力がここにはあるのだ。
おゑんは総籬の前を通り、美濃屋に入った。
「おや、先生、おいでなさいましたか」
顔馴染みの番頭が帳場から立ち上がる。美濃屋の前の番頭は吉原内で決して軽くない罪を犯した。火付けだ。仇を討つために吉原の一画に火を放とうとした。風の強い夜だった。一つ間違えば、吉原は猛火に包まれていただろう。
あの番頭がどうなったのか。今、生きているのかいないのか、おゑんには推し量れない。番頭もその一味も表立って咎められることはなかった。
火付けは重罪だ。放火炎上すれば火罪、火付けを命じた者も同罪となる。しかし、それは飽くまで大門の外での話。吉原には吉原の則がある。表立って咎めなしとは、吉原で犯した罪は吉原のやり方で贖(あがな)わせる、一切を秘して処すると、そういう意味になる。
番頭たちがどう咎を贖ったのか。どう罰せられたのか。知る由もない。
美濃屋の新しい番頭は猪吉(いのきち)という名だ。よく肥えていて、豊頬を揺らして笑うといかにも人の好(よ)い顔つきになる。その笑顔とは裏腹になかなか抜け目のない男でもあるからか、「あれは猪じゃなくて狐に近いな」と陰で謗(そし)られているらしい。もっとも、他人に謗られ、僻(ひが)まれ、煙たがられるようでないと吉原の番頭は務まらない。そういう意味でも、猪吉は遣(や)り手なのだろう。
「先生、お久しぶりですねえ。結構な嵐でしたが変わりはありませんでしたか」
「ええ、おかげさんで。何とか雨風に耐えられましたよ。美濃屋さんは相変わらず繁盛のご様子。何よりでござんすね」
「ええ、まあねえ。先生のおかげで女たちも病知らずで助かります」
当たり障りのないやりとりを交わし、おゑんは段梯子を上っていく。中途で足を止め、ちらりと下を窺うと猪吉もおゑんを見上げていた。
目が合う。遣り手の番頭の眼には、探るような光が宿っていた。
用心しているのだ。
美濃屋の花魁安芸は、美濃屋一軒に留まらぬ吉原の花だ。その美、その才を金に飽かして磨き上げた最上の品だった。その品を損なわれてはたまらない。傷一つない珠(たま)であってこそ、花魁の値打ちは高まる。そう、心にも身体にも生々しい傷をつけてもらっては困る。
先生なら、よくご承知でしょうな。
弛んだ瞼の下の眼がやけに鋭い。
おゑんは薄く笑ってみせた。それから、妓楼ならではの広い段梯子を上り切る。
昼見世が始まるのは、九つ時だ。まだ一刻ほどの間がある。
二階の廊下はそれなりに賑わっていた。
楼内の掃除を担う中郎が尻からげで床を磨き、新造と禿(かむろ)が居続けの客に出すのか、朝の膳を運んでいる。首に鈴をつけた三毛猫が二匹、笑い合う太鼓持と客の足元に並んで座っていた。火灯窓(かとうまど)から朝の光が差し込み、湯上りの遊女の肌を照らす。擦れ違った貸本屋の手代が軽く唇を窄(すぼ)め、遊女を目で見送った。
「先生」
禿が一人、駆け寄ってきた。
「おや、つるじ、ご無沙汰してたねえ」
安芸付きの禿の一人、つるじだ。明朗で聡明。よく気が回る。安芸は殊の外、目をかけ可愛がっていた。つるじもしっかりと仕え、それなりに花魁を支えている。
「元気だったかい。風邪とか引いてないね」
「あい。元気でありんす。先生もお達者でありんすか」
「おかげさまで、ね。あたしなりに、いろいろと気を付けてるんだよ。医者の不養生なんて思われたら、商売あがったりになるからね」
「あはっ、やだ、先生ったら」
つるじが禿から一人の少女に戻る。そして、屈みこんだおゑんの耳元に囁いた。
「花魁、ずっと待ってるよ。先生、早く」
小さな手に手首を掴まれ、引きずられるように廊下を歩く。その廊下の奥まった一室が花魁の本間だった。当然ながら、美濃屋で最も贅沢な座敷だ。
つるじがすっと体を引き、おゑんに背を向けた。
「お小夜さん、ゑんです。入りますよ」
声を掛け戸を開けると、ふわりと香が匂った。
「先生」
戸を閉めたとたん、浴衣姿のお小夜が胸に飛び込んできた。
「先生、お逢いしたかった。よかった、やっと来てくださったのですね」
「ええ、お小夜さんの文に釣られて、やってきましたよ」
「ほんとに、待ってたんです。あたし……先生だけを待ってた」
湯上りの身体も香を纏っていた。伽羅(きゃら)に似た仄かな香気が立ち上る。
花魁の身体は香木でできている――との噂は、まんざら作り話ではないのだ。
肌が香る。肌理(きめ)の細かさや滑らかさは、手入れ次第で我が物にもできる。しかし、この微かな香りは天性のものだ。床の中で身を熱くし、薄っすらと汗をかけば、香りはさらに艶を増す。一度安芸の客になれば、身代を潰しても、屋敷を売り払っても、通い続けられる限り通わざるを得なくなる。そんな噂もやはり、ただの流言蜚語ではない。
「お小夜さん」
おゑんは、花魁の背にそっと指を這わせた。
「湯上りにしては、ずい分と凝っていますね。何かありましたか」
「待ちくたびれました。もしかしたら、もう二度と先生にお逢いできないのではと考え、そうしたら怖くて……怖くてたまらなくなりました」
「まるで、道理を知らない子どものような物言いですね。あたしは、日を決めて通っているじゃありませんか。約定を反故にしたことは一度もありませんよ」
お小夜は顔を上げ、おゑんを見詰めた。
化粧(けわい)はしていない。けれど、頬はほんのりと紅く、唇はさらに紅い。肌が白いからだ。白が紅を引き立て、紅が白を際立たせる。
男は女だけが持つ、この美しさに魅入られ、溺れていく。
(この章、続く)