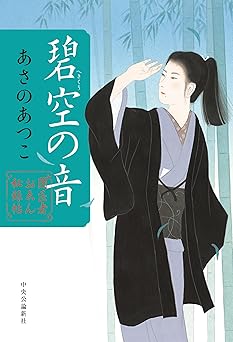「なるほど。気は小さい。けれど肝は据わっておられる。お話しすればするほど、おもしろい方だと思いますなあ」
「褒め言葉として、承っておきますよ、惣名主」
「むろん、褒めたつもりでおります。まっ、そんないらぬ話より、どうぞ一口、召し上がってみてください。この酒は異国のものではありますが、葡萄(ぶどう)から作られるのだそうですよ」
平左衛門は玻璃の器を持ち上げ、軽く振った。赤紫の酒が揺れる。
「葡萄……甲州で作られているという、あの?」
「ええ。山葡萄とはまた違う種で、蔓が伸びて実を付けるのだそうです。その実がどうやれば酒になるのか、見当もつきませんが。まあ、日本の酒は米からできるのですから、葡萄からできる酒があっても不思議ではありませんでしょう。世界は広い。我々が想像できぬような酒も料理もたくさんあるのでしょうな。きっと」
「ほんとに、どこまで広いのか、この目で見てみたい気もしますねえ」
「なされば、よろしい」
「はい?」
「先生なら、できるのじゃありませんか。海の向こうの国々を見て回る。そんなことも難しくはないような気がしますが」
「ご冗談を。自分の周り五間ほどの出来事にあたふたしているのに、海の向こうになんて、思いが及びませんよ。ああ、でも……」
珍陀酒に口を付け、平左衛門は問うように首を傾けた。
「惣名主はご存じでしょうが、あたしの祖父は海の向こうから、この国に流れ着いた者です」
知っているとも知らなかったとも、平左衛門は答えなかった。
知っているのだ。
おゑんを吉原に招き入れるとき、おゑんの身辺をできる限り調べたはずだ。吉原の網は粗くも細かくもなる。事の大きな要だけをすくい取るかと思えば、些細な事実を逃さなかったりもする。もしかしたら、祖父の死に纏(まつ)わるあの惨劇もまた、惣名主は承知しているのかもしれない。
「ですから、祖父の国がどういうところなのか、この目で見てみたいという気持ちはありますね」
どんな風景があり、どんな人々が暮らしているのか。
海はあるのか。山々は高いのか。空の色は青く、夕暮れ時は橙(だいだい)色に染まるのか。どんなものを食べ、どんなものを着ているのか。医者による治療はどう行われ、患者はどう扱われているのか。女が幸せに生きていける国なのか。理不尽に虐げられてはいないのか。女の心一つで、子を産むことが許されているのか。女たちは泣いて諦めるしか道はないと思わされてはいないのか。うずくまったまま、立てずにいるのではないか。
この目で見てみたい。肌で感じてみたい。女たちの声を聞いてみたい。
そういう気持ちはある。
「でも、その国の名前もどこにあるのかもわからないのです。雲を掴むような話じゃありますけどね。でも、夢物語としてはおもしろいでしょう」
「お調べになればよろしいでしょう」
こともなげに、平左衛門が言う。
「調べる? どうやってです」
「わたしも江戸から出たことがない身です。大層なことは言えません。ですから、ただの老人の世迷(よま)い言と思ってくれて構いません。それで、私が思うに、異国のことは異人に問えばいいのではありませんか。そのために長崎に行かれてはいかがです」
「長崎に?」
「ええ、彼(か)の地に行けば、異国の者と接することもできるでしょう。先生なら、異国の諸々を聞き出すこともできそうな気がしますが」
「川口屋さん、そんな容易く言わないでくださいな。長崎なんて、とんでもない。あたしには手の届かない遠国ですよ」
「そうですか。先生でも難しいですか。いや、先生ならやろうと思えばできましょう。これまでもそうだったではありませんか。先生はずっと、自分のやるべきことを為してきた。些かもぶれずにね。ならば、長崎の……いや、異国の地を踏むこともできるはず。先生ご自身が望まれれば、ですが」
「惣名主、あたしに長崎遊学の費えを出してやろうと言ってるのですか。それとも、江戸から出て行けと脅しているのですか」
「どちらでもありません。ただ、わたしから見ても先生は底の知れぬお方だ。だったら、その底を知りたい、覗いてみたいと興が湧いただけのことです。先生が異国の道を歩いている。そういう姿も含め、底に何があるのかをね。はは、これも年寄りの粋狂に過ぎませんかねえ。それとも、花魁の想いに重なるところがあるのか……。今度、甲三郎とじっくり話をしてみますか」
なぜここで甲三郎の名が出てくる? 出してくる?
もう一口、酒をすすり、平左衛門は促すようにおゑんを見た。
おゑんも玻璃の器を口に運ぶ。
珍陀酒と名の付いた酒は、しっとりと舌に馴染んできた。酸っぱくはあるが、それが邪魔にならない。底に甘みを秘めた味は深く、柔らかだった。
「おや、これは美味しい」
「でしょう。日本の酒とは違う、コクがある」
「ええ。でも危ないですね」
「危ない? この酒が?」
「そうです。ねっとりしたコクは苦味を隠します。この酒なら毒を入れられても、大半の者は気付かないかもしれませんね」
「わたしが先生を毒殺しようとしているとでも?」
「そんなことは申しませんよ。あたしの舌は薬には聡いですからね。毒薬が入っていれば、すぐに吐き出します。それに、惣名主があたしを始末しなければならない理由(わけ)が、今のところ見えてきませんしねえ。ええ、これは異国の美味しいお酒。ただそれだけですよ」
さらに一口、飲み下す。
「おもしろいことに、この酒には魚の甘露煮とか漬物とかが存外合いましてな。いかがです」
平左衛門が穏やかな口調で薦めてくる。
「あら、本当ですね。というか、この甘露煮、美味しいですよ。梅干を一緒に煮込んでいるのですね。見た目よりずっとさっぱりしていて、でも味はしっかりしていますねえ」
「喜んでいただけたら何よりです。おイノは昔から料理自慢でしたから、たぶん、先生も気に入ってくれると思っておりましたよ。もしよろしければ、お帰りのとき、この酒と甘露煮をお持ち帰りください。ご用意しておきますよ」
「まあ、何と嬉しいこと。今日は良き日になりました」
このまま立ち去れたなら、なかなかに良き日だったと言えるかもしれない。しかし、このまま立ち去れる見込みなど、万に一つもあるまい。
平左衛門が玻璃の器を置いた。
「先生、聞いていただきたいことがあります」
おゑんも箸を置く。
「お伺いいたしましょう」
聞く、聞かないを選べるはずもない。聞いた上で、異国の酒と甘露煮を手土産に大門を潜り、娑婆(しゃば)に出られるのなら御の字だ。
「先刻、先生は美濃屋さんで安芸とお逢いになった。安芸が先生をお呼びしたそうですな」
「ええ」
「安芸はどんな話をしました」
おゑんはわざと顔を顰める。
「川口屋さん、話が違いはしませんか。川口屋さんは、あたしに聞いてくれと仰ったのですよ。尋ねたいではなく、聞いてくれ、とね。だとしたら、あたしは耳を、川口屋さんは口を使うのが筋じゃありませんか。あたしがしゃべる番じゃありませんよ。それに、吉原の惣名主が、当代随一の花魁が口にした中身を知らないなんて、あり得ないでしょう」
あり得ない。全てを知った上で、平左衛門は問うてきたのだ。
何のために?
「先生、吉原の頂点に咲く花魁が、客でもない相手に文を出す。文を出し、お出でを乞う。これだけでも、吉原の理からは外れております。あ、いやいや、よろしいのです。何度も申しましたが、安芸が先生を慕っておるのは、ようわかっております。花魁だけではない、首代を束ねる男まで、どうも先生に現を抜かしておるようで、これはこれでまた困りものです。まあ、かくいうわたしも、先生に興をそそられておるのですから偉そうなことは言えませんが」
「おやまあ、惣名主さまの興をそそる。それは何とも豪儀なことですねえ。誉だと胸を張る前に、空恐ろしくなりますよ」
本音だ。喉元に刃を突き付けけられる方が、まだましだろう。
(この章、続く)