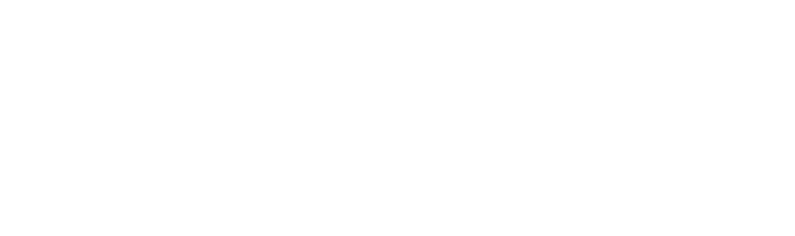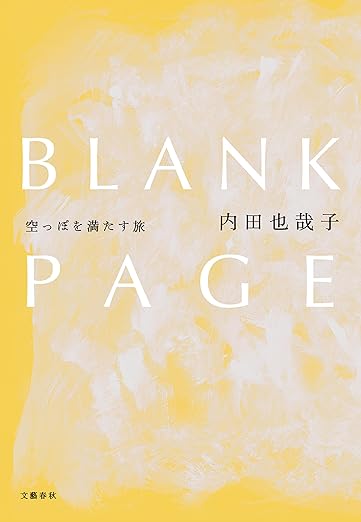「人間は孤独だ」という言葉の変化
振り返ってみると、私は一人っ子で、インターナショナルスクールに通っていたので近所の子どもたちとも距離がある。いつも、自分は浮いた存在だという寂しさがありました。
母は私が小さい頃から、「誰しも生まれてから死ぬまで孤独なんだよ」と私に語っていましたが、人と繋がりたいのにうまくいかなかった子ども時代、私はその言葉をネガティブにしか受け取れなかった。
19歳で本木雅弘さんと結婚して3人の子どもが生まれ、賑やかな家庭になりました。家庭に「父性」が存在するのが新鮮で、「あ、こんなふうに空気が変わるんだ」という気づきも。それでもやっぱり夫婦は他人同士だし、子どもといえども自分の一部ではないと感じます。だから、常に「一人ひとりは個である」という思いは変わりませんでした。
父も母も、私にとって強烈な存在で、彼らの子であることがちょっと重たくて、「あの人たちとは関係ない!」と言ってみた時期もありました。
でも、いざまるで神隠しにでもあったように2人ともいなくなると、彼らが残した大切な部分だけが思い出されてくるようになった。物理的な距離ができて初めて感じられる気持ちの存在を考えると、「人間は孤独だ」という言葉も、温かい考え方になり得るのかもしれない、と思います。
今回対話のほとんどを、対談の形ではなく、話した内容とその後の印象をコラージュのように組み合わせて書きました。「書く」というのは自問自答していく作業。私にとってはセラピーを受けるような大切な時間だったと思います。
ちなみに本の挿絵は次男の作です。8歳から13歳という、人間が一番変化していく時期でしたので、結果的にいい記録になりました。