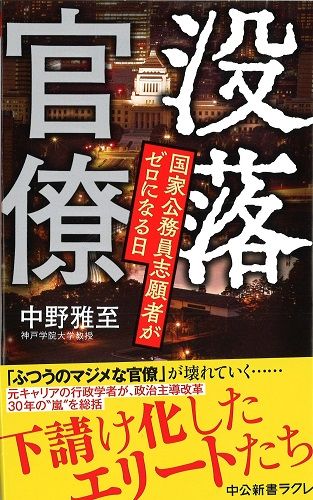新たな魅力が醸成されている気配がない
仮にエリートキャリア官僚制度が否定されているというのであれば、それに代わるような新たな魅力があればいいのだが、そのようなものが霞が関に醸成されている気配はない。
例えば、2017年に人事院が行った30代職員へのアンケート調査では、今後のキャリア形成の方向性について「どちらかというと自分の専門性・強みを高めていきたい」と回答した者が最も多かったが、従来と同じく人事異動のサイクルは非常に短く(2年~せいぜい3年)、特定分野の政策知識が深まらない。
その一方で、「上司からの支援の欠如」や「上司からの否定的な評価」もモチベーションの低下につながっている(「人事院白書」平成29年度に掲載の図7-2)。
さらに、若手実務担当者(係長級など)についていえば、外部からの苦情などカスタマーハラスメントに相当する言動への対応を余儀なくされている(「人事院白書」令和2年度)。
例えば、職員数が減っているにもかかわらず、苦情電話が増えている(2021年は前年に比べて少し減少しているものの)ことから、職員一人当たりが抱える苦情相談件数が激増していることも大きな要因となっている(「人事院白書」令和2年度に掲載の図1-3<6>)。
※本稿は、『没落官僚-国家公務員志願者がゼロになる日』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。
『没落官僚-国家公務員志願者がゼロになる日』 (著:中野雅至/中公新書ラクレ)
「ブラック霞が関」「忖度」「官邸官僚」「経産省内閣」といった新語が象徴するように、片や政治を動かすスーパーエリート、片や片や「下請け」仕事にあくせくする「ロボット官僚」という二極化が進む。地道にマジメに働く「ふつうの官僚」が没落しているのだ。90年代以降、行政システムはさまざまに改革され、政治主導が推進されてきたが、成功だったと言えるのか? 著者は元労働省キャリアで、公務員制度改革に関わってきた行政学者。実体験をおりまぜながら、「政官関係」「天下り」「東大生の公務員離れ」等の論点から“嵐”の改革30年間を総括する。