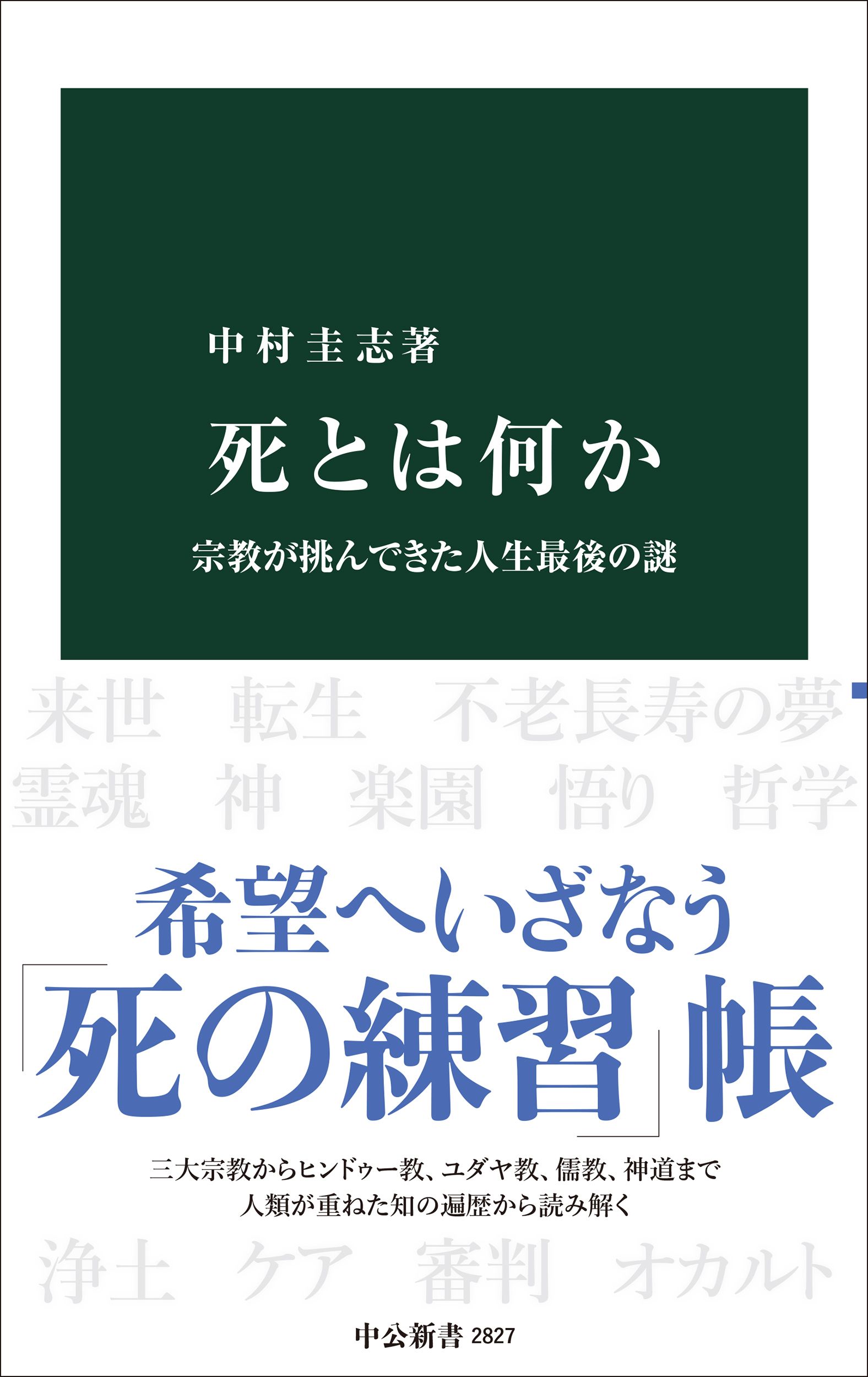来世観よりも切実な葬送の儀礼
ボイヤーは言う。哲学者や人類学者は、人間はみな根っからの《二元論者》であるために、身体の崩壊後の霊魂の行方のことで悩むのだ、と考えがちである。
しかし、実際に悩ましいものとなっているのは、もっと具体的なことである。物理的死も認め、意識の存続も感じてしまうという認知上の矛盾をめぐる葛藤こそが、人類を悩ませてきたのだ。
だからこそ、どんな社会でも、葬式は一般に死後世界を描くようなものではなく、死体とのお別れの複雑な手続きとなっているのである。
死体を丁寧に処置し、<精神は今や霊魂になったという約束を共有する>そういう移行の手続きなのだ。
重視されているのは来世観ではなく死体をめぐる儀礼だ、というこの見方は、日本人の来世観のことを考えると、確かに納得がいく。
日本人の来世観は、神道やら仏教やら道教やら儒教やら民間信仰やらが織り交ざって、黄泉(よみ)、常世(とこよ)、六道(ろくどう)輪廻、極楽浄土、幽冥界、村の裏山の先祖の世界……とさまざまに語られてきた。
要するに霊魂がどこへ行くのか分からない。矛盾だらけだが、誰もあまり気にしていない。
その一方で、葬儀は手の込んだものへと発達を遂げてきた。なるほど、大事なのは死者を送り出したり思い出したりする儀礼、葬式や法事であり、死者が今どういう場所にいて何を やっているかではないのだ。
実は、一見来世観がはっきりしているかに見えるキリスト教世界においても、実際にはさまざまな説が矛盾したままに語られてきたのである。
※本稿は『死とは何か-宗教が挑んできた人生最後の謎』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
『死とは何か-宗教が挑んできた人生最後の謎』(著:中村圭志/中央公論新社)
死んだらどうなるのか。天国はあるのか。できればもう少し生きたい――。
尽きせぬ謎だから、古来、人間は死や来世、不老長寿を語りついできた。その語り部が、宗教である。本書では、死をめぐる諸宗教の神話・教え・思想を歴史的に通覧し、「死とは何か」に答える。日本やギリシアの神話、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教から、仏教、ヒンドゥー教、そして儒教、神道まで。浮世の煩悩を祓い、希望へ誘う「死の練習」帳。