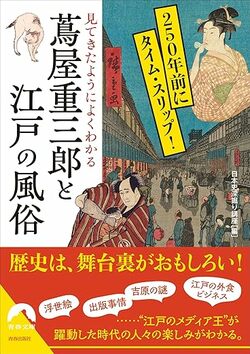「居酒屋」豆腐田楽からはじまった江戸の居酒屋文化
江戸初期の江戸では、各家庭でドブロクを自分で造って飲む人が多かったのですが、元禄年間になると、専門業者の造った酒が出回るようになりました。
酒の小売り専門店が登場したのです。ただ、その時代はまだ、買った酒を持ち帰り、自宅で飲むのが一般的でした。
その半世紀後の宝暦年間(1751〜1764)、蔦屋重三郎が子供の頃には、酒屋で買った酒を店先で飲むスタイル〈今でいう角打(かくうち)〉が広まりました。
そういう店は、店に「居るままで酒を飲ませる」ことから、「居酒屋」と呼ばれはじめます。
やがて、居酒屋のなかから、人気の店が現れます。神田鎌倉河岸(現在の内神田2丁目)にあった「豊島屋」です。
もともと豊島屋は、江戸初期、江戸城の改修で集まった職人や商人たちを相手に開いた店でした。
その後、店先で酒を飲ませる居酒屋となり、お客を呼ぶために、豆腐田楽を出したところ、これが大当たりしたのです。豊島屋の豆腐田楽は、1本2文(40円程度)と安く、しかもサイズが大きかったことから、お客が押し寄せたのです。