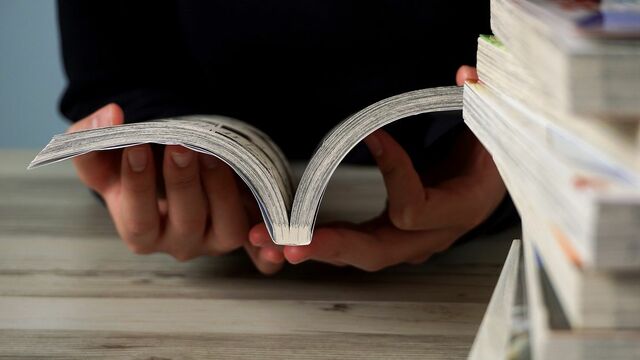現代の60、70代は、まだまだ若い一方、「老い」をどう受け入れていくかについて、考え始める世代でもあります。そんな時助けになるのが「知力」です。「インプットした情報はアウトプット」、「できないことには鈍感力を発揮」など日々の習慣が、60代からの自分を作り直してくれます。「身体」と同様に「知力」にも鍛え方や保ち方のコツがあると語る、身体と言葉の専門家・齋藤孝さんの著書『60代からの知力の保ち方』より一部を抜粋して紹介します。
不安や変化には、自分が慣れる
私は45歳の時、体調不良で1度倒れたことがあります。
この頃の私は「週刊齋藤孝」と言っていいほどのペースで本を出していました。自分は身体が丈夫だから、いくら仕事をしても大丈夫だという根拠のない自信があり、倒れた時は我ながら驚きました。
しかも、一時は命が危ぶまれる瀬戸際まで行ったのです。過労死の1歩手前です。
それからは「これはいけない」と、一気に仕事量を減らしました。それまで予定でびっしり埋まっていたスケジュール帳に、余白が目立ってくる。
やるべきことがなく手持無沙汰なのは、非常に不安でした。これは考えてみますと定年を迎えて直面する不安に似ています。
ぽっかり心に穴が開いたような状態でした。ところが、2カ月ほどたつと心に穴が開いたような状態にも慣れてきました。
すると、それがプラスの効果を発揮して、「そういえば、若い頃はだらけることが得意だったな」と、自分でも忘れていたことを思い出させてくれたのです。
私は20代のほとんどを大学院生として過ごしました。もちろん無給で、ひたすら研究をし、1日何の予定も充実感もなく、社会的な関係性からも遠ざけられていたのです。
そんな時代があったものですから、いきなり予定がなくなった状況を、もう仕方がないと1度割り切ると、不思議とあまり不安に思わなくなりました。