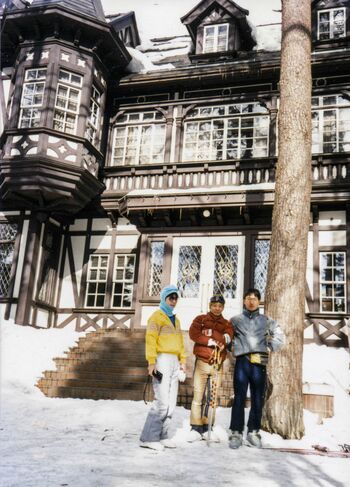富岡さんは特別だった
このころ、石坂は月に2度は玉川学園まで出かけ、富岡と近所をブラブラ散歩したり、町田に出てランチをしたりするようになった。「ひとつ星山岳会」と富岡が名付けた初心者コースの山歩きに出かけたりもした。山岳会の名前の由来は、山のガイドブックの一番簡単な初心者向けの山に星がひとつついているからだった。
「富岡さんのところに行くのはまったく苦じゃなかったですね。いい加減に帰りなさいって感じのときもあったけれど、1時間で帰ったことはないです。富岡さんはとにかく何事につけ感度がよくて、伊藤比呂美さんが出てきたときも、『良いおっぱい悪いおっぱい』をいいよと教えてくれたり、山田詠美さんが文藝賞をとってデビューすると早速読んで作品の要点を教えてくれました。文学に限らず、世の中のさまざま表現にアンテナを張っていて、いろんなことを教えてくれるんですよ。ガートルード・スタインとアリス・B・トクラスを描いた映画『月の出をまって』が公開されるとすぐに観に行けと勧められるし、柄谷行人さんの批評も富岡さん経由で新しさを知るわけです。こっちは素人に毛が生えた程度だから、富岡さんの言うことをスポンジが水を吸い込むようにどんどん吸収しました。富岡さんが言うことは理路整然としていてわかりやすくて、富岡さんを通してこの世界を見ていたような気がします」
そうした関係のなかではじまった「群像」の連載は、エッセイ「表現の風景」。富岡がダッチワイフや、女の表現などを縦横無尽に論じた。
「毎回毎回、もらう原稿が新鮮でした。当時は日本文学史に出てくるような作家がまだ生きていた時代で、治安維持法違反で牢屋にいた作家もいるし、第一次戦後派も近代文学派も元気でした。女性作家では佐多稲子さん、円地文子さん、野上弥生子さんも健在で、瀬戸内寂聴さん、河野多惠子さん、大庭みな子さん、津島佑子さんたちが第一線でした。まだ女流文学と呼ばれていて、女流文学者会があり女流文学賞があった。富岡さんは、女流というなら男の文学も男流文学と呼ぶべきだと言ってましたね。そんなころに発表された『表現の風景』は斬新でした。自分ひとりで考えたことを自分ひとりの責任と言葉で自由自在に書く、といった潔さがあった。担当小説家のなかでも富岡さんは特別でした。いつも最前線で我が道を行くといった感じで、とにかくカッコよかったです。でも、自分は富岡さんのひとりの戦いの本当の大変さは、そのころはまだわかっていませんでした」