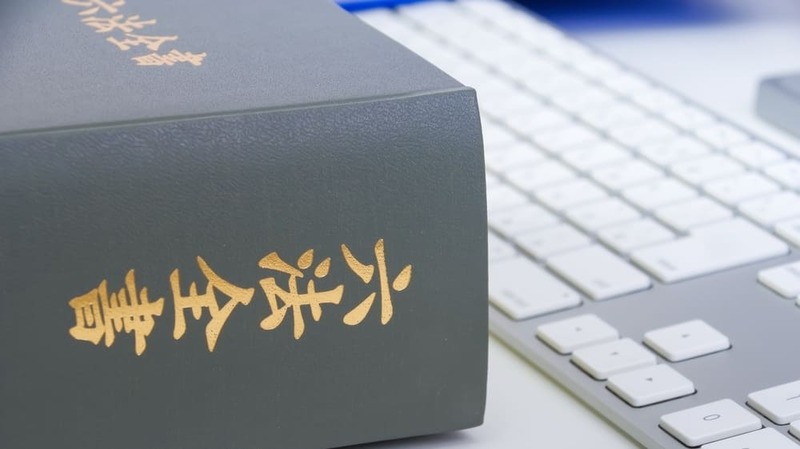2009年に裁判員制度が始まり、以前よりは裁判が身近になったとはいえ「自分には関係ない」と思っている方も多いのではないでしょうか。そのようななか、令和6年に再審無罪が確定した袴田巌さんの事件を例にあげ、「日本国民であるあなたは、捜査官が捏造した証拠に基づき死刑を執行される危険性を日々抱えたまま生きている現実を知らなければなりません」と語るのは、元判事で弁護士の井上薫さん。そこで今回は井上さんの著書『裁判官の正体-最高裁の圧力、人事、報酬、言えない本音』から一部引用、再編集してお届けします。
デジタル化の功罪
最近、デジタル化が進行してパソコンで処理することが増えました。仕事の種類にかかわらず、実際やっていることはパソコンをいじっているだけということが多くなりましたが、裁判もそうです。
法廷でされることを全部デジタル化するということは今のところできていませんが、ここまでデジタル化が進展してくるとどうなるか分かりません。
法廷外の仕事のうち法律や判例を調べるという分野が、最もデジタル化が進んでいるかと思います。条件を入れて判例を見たいとパソコンに聞けば、こういうのがありますとたくさん出てきます。条件を絞って数件くらい実際の判決を読んでみるかというようなことが行われています。デジタル化によって非常に作業が早くなりました。
それがない場合は、判例集という紙でできている本を読んでそれで判例の中身を理解したわけです。ただ、判例というのも膨大な量になっていますので、肝心の要点が載っているところに到達するのにかなり時間がかかります。特にあまり有名でない判例を調べる場合などはそれを手に入れるだけでもかなり時間がかかっていました。そういうことを考えると、デジタル化はプラスの面があります。