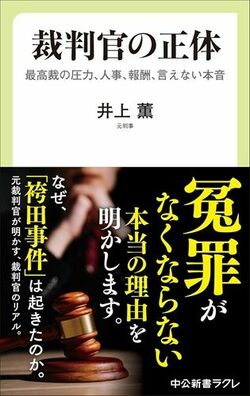判決を書く負担
和解をするとその事件は一件落着となり、事件は終わってしまうので、当然、裁判官は判決を書く必要がなくなります。書きたくても書くこともできなくなります。この辺の事情は、あるいは国民一般はあまり知らないのかもしれませんね。でも、この和解による効果というのは、裁判の現場では重要性があります。
つまり判決を書く労力がゼロになってしまうわけですから、これは裁判官にとってみたらかなり労力の減少になります。
判決は、双方の主張と立証を全て頭に入れて、裁判官が考えをごちゃごちゃとまとめて結論を出してこれを文章化する作業の結果生まれるのです。判決の文章の量ですけれども、事案によりますが、たとえば複雑な事案であったり、当事者が多いとか、相反する証拠がたくさんあって判断が微妙だなという場合、あるいは憲法問題のような重要な法律問題がある場合、また前例がないケースという場合、これらの場合には裁判官が判決を書く負担はかなり大きくなります。
これらの事情が複数含まれる場合はますますその負担が大きくなると思います。裁判官も楽をしたいと思うならば、判決しない方法を考えるしかなくなります。できれば和解に持ち込みたい。そういう心理が常にあります。