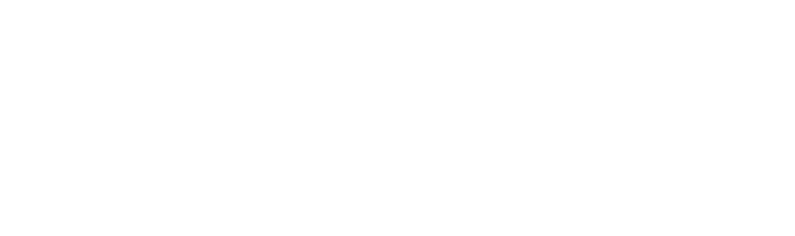《背骨》のような存在が消えて
帰宅した美土里が、自宅の階段で転倒する場面があります。実は私も2回、階段から落ちました。私は幸い骨折せずにすみましたが、夫が亡くなると、女は「骨を患う」ことがある。車椅子生活になった人や、脊椎を傷めた人もいます。
夫婦の関係がどうあれ、長い間傍(かたわ)らにいた、《背骨》のような存在が消えて、精神的に参ってしまうのでしょうか。かと言って、生きている間に夫を大事にしろといわれても難しい話ですけどね。(笑)
同じ未亡人仲間の友だちに話を聞き、ネットや本で調べれば調べるほど、女たちの嘆き方、悼み方は千差万別であることが見えてきます。書きたい場面や題材が、次々と湧きあがりました。
仏壇に灯したロウソクの赤く揺らぐ火。娘夫婦と初めて読経したコロナ下の初盆。家にあった『地獄草紙』の図版。お盆に故人の魂を子孫が背負い、墓地から家へと連れ帰る「お精露(しょうろ)さま」の風習。
それらを繋げて物語にするのに、ひとつひとつ、納得がいくまで資料を読みこみました。
美土里と同じころに未亡人となった美子(よしこ)は、亡夫が時計職人の仕事と野鳥を観察する趣味三昧(ざんまい)の、「離れ小島の住人」だったと話し、心が通わなかった結婚生活を匂わせます。
それでも、夫がこよなく愛したタカの一種・ハチクマの渡りを美土里たちと見送りながら、そっと涙を流すのです。実際に「ハチクマが来るよ」と私に声をかけてくれる人があり、「行く行く」と駆けつけては、美土里のように空を眺めました。