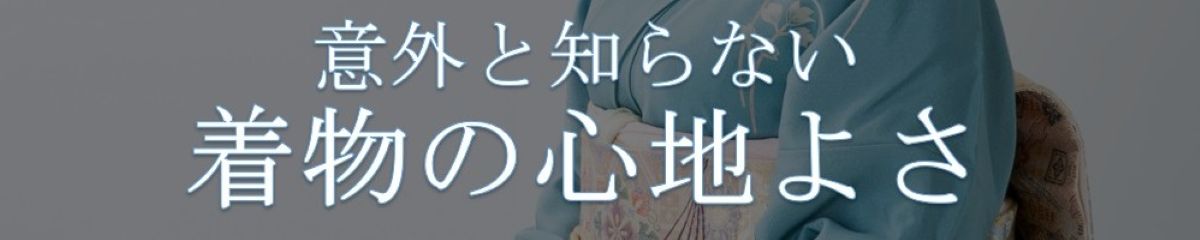なぜ絹の着物は水洗いできるのか
「え? 洋服にだってシルク素材はある、だから着物の特権みたいに話すのはおかしいよ」と、思われた方もいたかもしれません。
確かに絹で作られた洋服もありますが、クローゼットに収納した服全体から考えると、割合はかなり少ないのではないでしょうか。
その背景として、基本的に「絹の洋服は水洗いできない」という特性が影響しているように思います。
絹は水をかけると縮みます。だから多くの絹の洋服は水洗いを避け、ドライクリーニング推奨となります。これはつまり、水性洗剤の類は使えず、ドライ洗剤のみ使える、ということです。
しかしそれでは油性の汚れしか落とせない。水性の汚れ、たとえば汗じみなどは、しみ抜き処理で部分的に落とすしかなくなります。
対して、絹の着物が水洗いできるのはなぜか。それは仕立て方の違いに起因します。
洋服は着る人の体の線に合わせて仕立てる【=曲線立ち】ため、30%程度の生地を捨ててしまう。ですので、もとの生地の形に戻すことはできません。
一方で着物は、袖、体の前、後ろに当たる部分…と、全部大小の四角形の集合で裁断し、余る部分は四角形の端に縫い込んで生地を捨てずに、仕立てていきます【=直線裁ち】。
そのため糸をほどけば、また一反の反物に戻すことができる。そしてその反物を、ピンと張って【=伸子張り(しんしばり)】水洗いすれば、縮むことなく洗いきれるのです【=洗い張り】。
暑い季節にこそ活躍する絹の着物、この夏、ぜひ挑戦してみてくださいね。