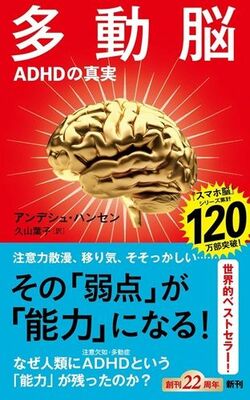SNSでもらえる「小さなごほうび」
インターネットもそれとまったく同じ仕組みだ──とリンデンは主張する。SNSでもらえる「いいね!」の1つ1つが脳の報酬系(人間をやる気にさせる、脳の奥深くにある豆ほどのサイズの脳細胞の集まり)に小さなドーパミンのごほうびを与えているのだ。たいして大きなごほうびではないが、ポジティブなことと認識できる程度ではある。
フェイスブックの「いいね!」は犬を訓練する際の大きな報酬(肉の塊)ではなく小さな報酬(肉のかけら)の役割を果たし、それが100回繰り返されると行動(スマホを見ること)が少量のドーパミンをもらえるという結果にはっきり関連づけられる。
小さな肉のかけらを繰り返し与えて犬を訓練するように、何度も繰り返すうちに人間の脳の中で「スマホを見ること」が「ドーパミンのごほうびをもらうこと」とつながり、それが強い衝動になって、テレビ番組が格別面白くはなかったり相手の話が少しでも長くなったりした途端にスマホに手が伸びるのだ。
ADHDの人にとってデジタルな世界はひときわ魅力的だ。活性化しづらい報酬系は常に低空飛行状態なので、スマホが与えてくれる小さなドーパミンのごほうびがこの上なく魅惑的に感じられる。報酬系が鈍い人にTikTokやスナップチャットを使わせるのは、溶けそうなほど暑い日に10キロ走った人に水のペットボトルを渡すようなもので、とても抗えない誘惑になる。
スマホは報酬系を活性化させるように開発されているので、学校は生徒の「注目」を巡って苦戦を強いられる。教室で先生が話すのを聞くのとデジタルの世界の楽しさは雲泥の差だからだ。つまりデジタル機器のせいでADHDになるわけではなく、ADHDの傾向が強い人にとって抗いがたい存在だということだ。とりわけスマホからは素早くごほうびをもらえるせいで、授業がますます退屈に思えてしまう。