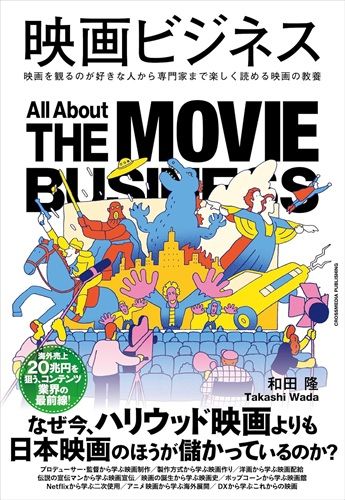映画番組の役割は非常に大きいものだった
以上、地上波の映画番組の変遷をまとめてみましたが、私がこの記事で主張したいのは、バラエティやドラマ、ニュース、情報番組と同じように、テレビを点ければ映画が毎日のように見られる時代があったということです。
前知識も少なく、夕飯やお菓子を食べながら何気なく見ていた作品にいつの間にか引き込まれ、未知の世界を知り、その後の人生にまで影響を与えるような映画との出合いの場が、そこにはあったのです。
核家族化や人々の生活スタイルが変わり、リアルタイムで地上波の番組を家族で一緒に見ることが少なくなっていったことで、視聴率が取れなくなり、映画番組が減っていったと思われますが、映画との出合いの機会を毎日のように作っていた映画番組の役割は非常に大きいものだったのです。
質の低下やマンネリ、ハリウッドスターの高齢化、多様化など他にも理由はありますが、昨今の国内における洋画興行の低迷の要因のひとつには、地上波の映画番組の減少による、この習慣化が失われたことも影響しているのではないでしょうか。
※本稿は、『映画ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。
『映画ビジネス』(著:和田隆/クロスメディア・パブリッシング)
本書は、17年間にわたり映画業界紙の記者として第一線で取材をしていた著者が、映画産業の仕組みと現状を徹底解説する一冊です。
製作から配給・興行、二次使用まで、映画ビジネスの全工程を網羅し、業界の最新動向や課題、未来の展望までを詳しく解説します。
さらには、著者が取材のなかで目撃した映画業界の驚きエピソードも満載。映画ビジネスについて楽しく学ぶことができます。