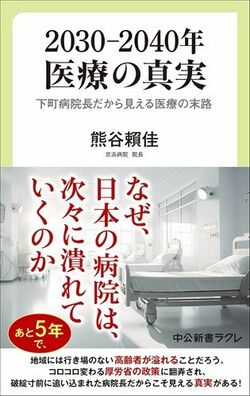尾上縫事件の余波
ちなみに、銀行が個人への事業資金の貸し付けを渋るようになったのは、1991年に発覚した尾上縫事件がきっかけだ。日本興業銀行(現・みずほフィナンシャルグループ)などが、大阪ミナミの料亭の女将だった尾上縫個人に2400億円もの融資をして焦げ付かせるという前代未聞の詐欺事件だった。尾上は信用金庫の支店長らと結託して架空の預金証書を作って担保の差し替えをし、14もの金融機関から総額2兆7000億円にも上る融資を引き出した。この事件を機に当時の大蔵省は、金融機関に対して個人に対する高額貸し付けを見直す指令を出した。
この事件の余波が色濃く残っていたこともあり、新たな資金提供を受けようとしたところ、私たちの病院のメインバンクだった大手銀行に、医療法人にしなければ新たな貸し付けはできないと迫られたのだった。だが、病院として借金があるままでは医療法人にもできない。
父は最後まで医療法人化に反対したが、ここで病院が倒産し、長年一緒に働いてきたスタッフを路頭に迷わすわけにもいかない。かなり悩んだ挙句、銀行から提案された最善策は、個人病院である京浜病院と新京浜病院の借金を全て父・熊谷頼明(「頼」は、正しくは旧字体)個人名義にして病院自体の借金はなくし、個人病院を医療法人化することだった。医療法人にすれば、億単位の借金が病院ではなく、父の名義になる。父が頑なに医療法人化に反対し続けたのは、医療法人にすれば、病院の収入を借金返済に回すことができなくなり自分が全ての負債を背負うことになるからだった。
それでも、父の反対を押し切って2000年に医療法人を設立した。新たな資金提供を受け、介護保険導入と同時に介護療養型病院に転換したこともあって、しばらくの間、病院経営は安定した。2006年にはメインバンクを変更し、経営にも余裕が出てきた。2007年からは地域での介護技術の向上と普及を目指して京浜介護研究会を開催し、大田区以外からも大勢の参加者が集まるようになった。
京浜病院を急性期の一般病院から介護療養型の病院へ転換させて以降、高齢者医療と認知症ケア、とりわけ対応が難しい認知症の精神心理症状と行動障害(BPSD)の改善が、私のライフワークとなっていた。もともと脳神経外科である私は、看護師や介護スタッフと一緒に、周囲を困らせるBPSDの解消に有効な介護法である「熊谷式認知症3段階ケア」を構築した。
「熊谷式認知症3段階ケア」は、特に、実際に認知症の患者と日常的に接している看護師や介護職員にとても好評で、各地で講演会に呼ばれるようになった。認知症のタイプ別の対応法をまとめた著書『カラー図解 介護現場ですぐに役立つ! タイプ別対応でよくわかる認知症ケア』(ナツメ社)は、5万部も売れ、2017年に著したものだが未だに認知症の講習会などで使われている。