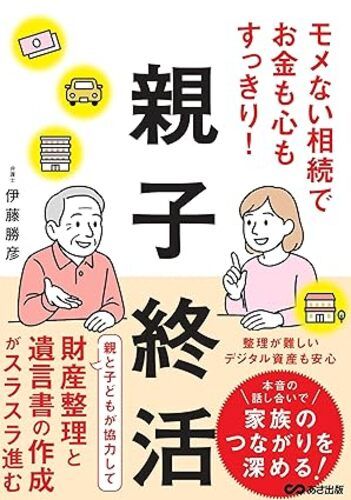「一次相続・二次相続」の両方を想定
相続対策では、夫婦のどちらが先に亡くなるかによって、とるべき対策が変わってきます。そのため、「夫が先に亡くなるケース」と「妻が先に亡くなるケース」の両方を想定したシミュレーションをしておきましょう。
配偶者が相続する場合、相続税について優遇措置が設けられています。配偶者の税額軽減措置により、配偶者が相続する財産のうち1億6,000万円まで、または1億6,000万円を超えた場合でも配偶者の法定相続分までは相続税がかかりません。これに対し、子どもが相続する場合はこうした大幅な軽減措置がありません。
例えば、夫が亡くなった場合、妻への相続では軽減措置が適用され税負担が軽くなりますが、その後妻が亡くなり子どもが相続する際には、通常の相続税がかかります。一方、妻が先に亡くなり夫が相続する場合も、夫から子どもへの相続時に同様の税負担の問題が生じます。
このような二段階の相続(一次相続・二次相続)を見据えたシミュレーションを行い、家族全体として最も税負担が少なくなる方法を検討することが大切です。
なお、相続税の申告と納付は、相続が始まった(つまり被相続人が亡くなった)日から10カ月以内に行わなければなりません。申告先は亡くなった人の住所地を管轄する税務署です。
※本稿は、『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』(あさ出版)の一部を再編集したものです。
『モメない相続でお金も心もすっきり!親子終活』(著:伊藤勝彦/あさ出版)
本書では、家族全員で協⼒し合いながら親の終活をスマートに進めるための5つのステップを提供。
遺産相続や遺言書作成、金銭面における不安を大きく軽減するだけなく、親⼦のコミュニケーションが円滑になり、家族の絆も強化されます。