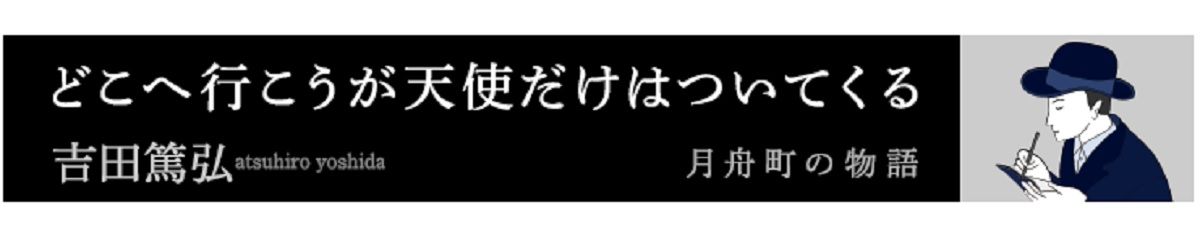母の手帳は、この部屋の水色の引き出しにしまってあった。
皆がいなくなってしまったあと、教会にひとり居残り、小さな黒い手帳に朗読会の下書きを頼りない細い字で書いていた。
「ゆっくりと少しずつ動いてゆく」
予定していた朗読会に母はそのような表題を準備していた。長らく探求していたテーマだった。少しずつゆっくりと動いてゆき、やがて、「遠方」にたどり着いて荷をほどく。
母は詩のようなものと、気ままに湧き出てくる思索を、手帳やノートに書きとめ、定期的に朗読会をひらいて人前で披露していた。
望まれてはいたが、本は一冊も書かなかった。残されたのは、夜の教会で読み上げられた朗読の残響と、小さな黒い手帳に書きとめられた言葉の断片だけだ。
手帳の最初のページにこうある。
「世界をこしらえるときに神様は愉しんだに違いない。そう思いたい。いま、ここにこうしてあるものは、これすべて、誰かが愉しんだ結果である。そう思うと、世界全体がひどく愉快に見えてくる」

母はそして、ガラクタをたくさん部屋に残していた。
ガラクタという言い方は、わたしではなく母の言葉だ。たしかにそう見えるものもあるし、まったくガラクタには見えないものもある。
人類の営みをかえりみたとき、その行き過ぎた進化と驕りに対して自嘲する思いが勝っていれば、わたしたちを取り囲んでいる様々な物象は、すべてガラクタに見えてくる。人類は余計なものをつくりすぎた──という自戒が、文明の利器と呼ばれているものをガラクタとみなしていく。
それが母の「ガラクタ」の理だが、手帳にはこんなことも書いてあった。
「便宜性だけで物と接していると、人間にとっていちばん大切なものがこぼれ落ちてゆく」
そう書いて、一行の空白を置き、
「これはしかし、物質的に豊かな時代を生きる者の、もっともらしい戯言に過ぎない」
と追記していた。
母は「もっともらしい」ことを嫌っていた。支持されることを期待して、もっともらしいことを言うのは、「言葉の無駄づかいでしかない」と。
母の残したガラクタを整理するのが当面のわたしの仕事ということになる。いや、「整理」というのも、もっともらしい言葉のひとつだろう。
ようするに、捨てていくということだ。