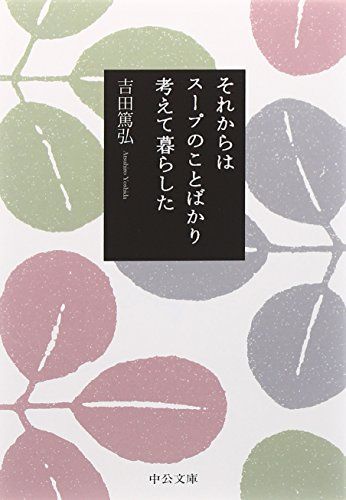話がたまごパンに戻り、「いただきます」とひとつ分けてもらった。まだ、冬眠は始まっていないのに。
「みどり先生がいなくなって、世界はいよいよつまらなくなってしまった」
彼は詩文の一行一行を書くように話した。
「いいんだよ、僕はもう。ただ気ままに貧乏に暮らしていければ。つなわたりの細いロープを渡って──そういえば、こないだね」
急に話が変わる。
「こないだ、長いあいだお世話になった自動販売機が撤去されて、いつもの缶コーヒーが買えなくなった。犬なら、『鼻が乾く』というやつだよね」
心許なさを紛らわすように彼が喋りつづけているのに、老犬のフジオカは部屋の隅のバスタオルの上で「どこ吹く風」とばかりに眠っている。
実家から送られてくる林檎を箱ごと大家さんに献上し、どうにか犬と暮らす許しを得ている。おとなしい控えめな犬。いるのかいないのか分からないくらい、寝息すら静かな犬。
「僕らのアパートは」
と彼はたまごパンを齧りながら天井を見上げる。門司君の「僕ら」は、彼とフジオカのことだ。彼とわたしのことじゃない。
「なんだか、嵐の中の舟みたいだよね。救急車のサイレンとか、予想外の大雨なんかが窓の向こうにあって。お金はないし、仕事もつなわたりで、缶コーヒーを買えなくなって、みどり先生までいなくなってしまった」
でも、貧乏は気ままだから、と彼は言った。
本当にそう。お金を落としたり奪われたりする心配がない。
ご馳走を望まない。旅行にも行かない。ぴかぴかの金時計が重たくて疲れることもない。
こうしてふたりでいれば、恐いことは何もない。幸せのことなんか微塵も考えない。幸せのことを考えると不幸せになるだけだから。
お湯が沸く薬罐の音。はためくTシャツ。静かな犬の寝息。ぼろぼろとこぼれ落ちるたまごパン。古い本。遠いサイレン──。
大雨の中を舟はゆく。
ガラクタを乗せて、ゆっくりと少しずつ。