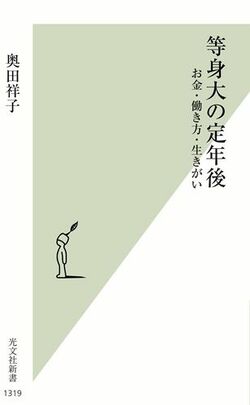「臭い物に蓋をしない」メンタルヘルス担当者
田川さんと出会ったのは、2006年。管理職ポストの削減や社員のリストラの進行と同時に、職務の個人化や職場のコミュニケーションの希薄化が進み、メンタルヘルス不調を訴えて欠勤、休職する社員が増加し始めていた時期だった。ただ、当時、新聞やテレビなどマスメディアが報道することはなく、水面下で深刻化する問題の取材に協力してくれる企業の人事、労務担当者はなかなか現れなかった。
そんな状況下で、「臭い物に蓋をせず、これからの会社と社員のためになるなら」と、快くインタビューに応じてくれたのが、大手IT企業で人事部の課長として、社員のメンタルヘルス対策を担当していた当時43歳の田川さんだったのだ。
初対面の挨拶もそこそこに、田川さんは適応障害やうつ病など心の病の診断書を提出して会社を休む社員が増加している背景と要因について、こう熱弁を振るった。
「諸悪の根源は、成果主義です! かつてはともに助け合ってチームとして実績を上げて前進していくことが目的だった仕事が、成果主義人事制度が導入されてから、隣の席の同僚、年次の近い先輩、後輩が人事考課を競い合うライバルになってしまったんですから……。査定は昇格、昇進とともに、賃金に直接影響しますからね。管理職の上司だって、一次考課者の課長から二次考課者の部長まで、自分を審査する人間なわけですから。自分の仕事だけに打ち込むことになって、悩みを誰にも相談できないまま……心を病んでしまうのも当然ですよ。そのことで労働生産性が低下して、結果、会社は損失を被る、という悪循環に陥りつつあるのが現状だと思います」
成果主義人事制度は、日本では1990年代後半から大企業を中心に導入され始め、今では広く浸透している。実績や能力に応じた給与など処遇を決めることにより、社員の働くモチベーションを高め、生産性向上にも効果があるとされているが、人件費削減策としての色合いも濃い。
田川さんは筆者が仮説として考えていた段階だった、成果主義による職務の個人化や職場の人間関係、コミュニケーションの希薄化が、メンタルヘルス不調を訴える社員の増加に大きな影響を与えているという因果関係を、現場の声としてズバリ、証明してみせたのだ。