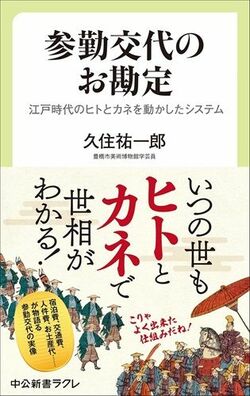次々に大名屋敷が建てられていった
参勤交代が制度化されると、大名は隔年での江戸居住を強制され、妻子も江戸の屋敷で暮らすことが義務付けられた。こうなると全ての大名が江戸に屋敷を与えられることになり、次々に大名屋敷(江戸藩邸)が建てられていった。また、屋敷内に居住する人が増えて手狭になると、複数の屋敷を拝領する大名があらわれた。
明暦3年(1657)1月に起きた大火により江戸の街の約6割が焼失したことは、大名屋敷の郊外への拡大を加速させた。その結果、ほとんどの大名が複数の屋敷を持つことになった。各屋敷はその役割によって上屋敷・中屋敷・下屋敷などと呼ばれた。
上屋敷は江戸城に近い場所にあった。江戸滞在中の大名が住む場所であることから、居屋敷とも呼ばれた。大名の正室もここで暮らした。江戸における藩の行政機構も置かれ、幕府や他の大名との窓口の役割も果たした。
中屋敷は上屋敷のスペアであり、隠居した大名や大名の世継ぎが暮らした。
下屋敷は江戸城から離れた場所にあり、敷地面積も広かった。上屋敷が火事になった場合の避難場所であり、広大な庭園を持つ別荘地や接待場所としての役目もあった。江戸藩邸に造られた大名庭園は、小石川後楽園(水戸徳川家上屋敷)や六義園(りくぎえん)(郡山藩主柳沢家下屋敷)のように、現在でも庭園や都市公園として利用されている例がある。
また、4代将軍徳川家綱政権による大名統制策の緩和により、末期(まつご)養子が認められるようになったこと、大名重臣の子弟を人質として江戸藩邸に置く証人制が廃止されたことにより、大名屋敷が江戸城から少し離れた広い場所に移転することもあった。加賀藩主前田家の上屋敷が大手門前から本郷へ移転したのはその一例である。